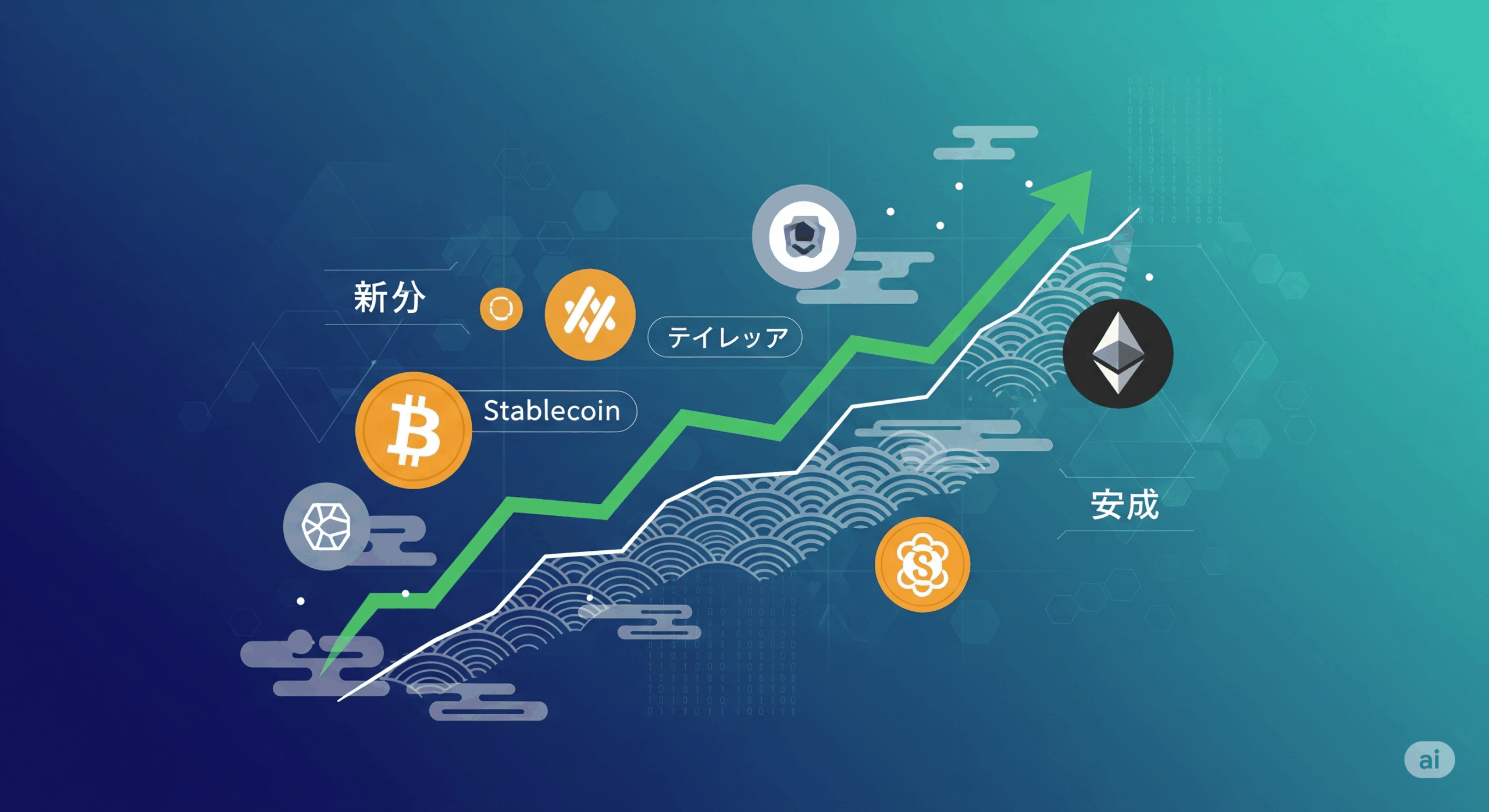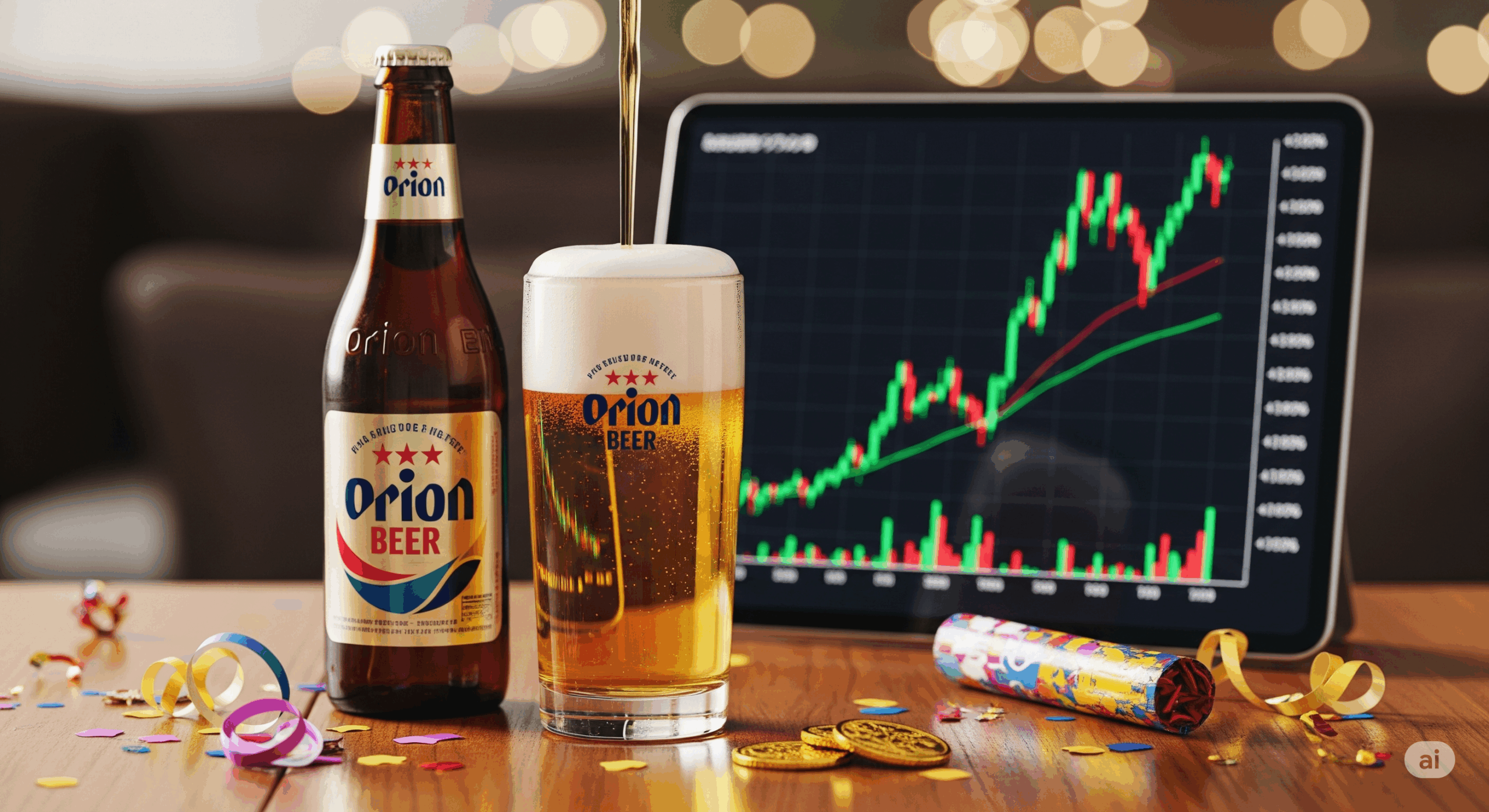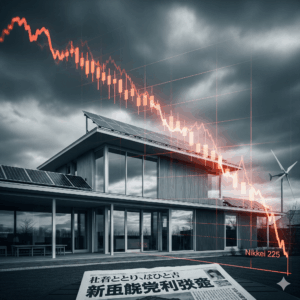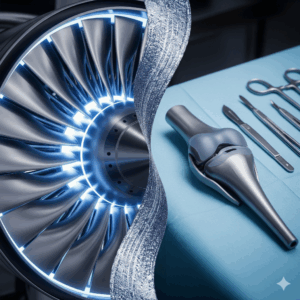タワマンパラドックス:東京の不動産ブームを巡る神話の解体

「タワマンバブル」という言葉がメディアを賑わせ、久しくなりました。特に首都圏、とりわけ東京23区におけるタワーマンションの価格高騰は、もはや社会現象と化しています。この熱狂を前に、一つの有力な仮説が長らく語られてきました。それは、「相続を控えた高齢の超富裕層が、その主要な買い手である」というものです。
この仮説の論理は明快でした。まず、日本において純金融資産1億円以上の「富裕層」および5億円以上の「超富裕層」の資産総額は過去最高を更新し続けており、この莫大な富を次世代へ効率的に移転させるニーズは極めて高いとされます。ここで、タワーマンションが持つ特有の税制上の利点、いわゆる「タワマン節税」が注目されます。これは、市場での売買価格(時価)と、相続税を計算する際の基準となる評価額との間に生じる大きな乖離を利用して、相続財産を圧縮する手法です。この「相続対策需要」を見越した投資家たちが、将来的に高齢富裕層へ売却することを目的にタワーマンションを先行取得し、活発な転売市場を形成している、という二次的な仮説も生まれました。この一連のサイクルが、現在のタワマンバブルを支える根幹のメカニズムであると想定されてきたのです。
しかし、この広く受け入れられてきた仮説は、今日の市場の実態を正確に捉えているのでしょうか。それとも、データは全く異なる「犯人像」を指し示しているのでしょうか。本稿では、この「高齢富裕層の相続対策需要」という神話を徹底的に検証します。市場価格の動向、需給バランス、建築コストといったマクロな市場データから、実際の購入者層のデモグラフィック、そして決定的転換点となった税制改正の影響まで、多角的な視点から分析を行い、古くなった神話を解体し、2025年以降のタワーマンション市場を動かす、より複雑で進化した新たなパラダイムを構築します。
第1章:市場の解剖学:供給、コスト、そしてグローバル資本
現在のタワーマンション市場を「バブル」と一言で片付けるのは容易ですが、その実態は複数の要因が複雑に絡み合った結果です。価格高騰の背景には、単一の需要層だけでは説明できない、市場構造そのものの特異性が存在します。単純な需要側の熱狂だけでなく、供給側の制約とグローバルな経済環境が、現在の市場を形成する上で決定的な役割を果たしています。
価格高騰という紛れもない事実
まず、価格の上昇は疑いようのない事実です。不動産経済研究所によれば、2023年の東京23区における新築マンションの平均価格は1億1,483万円となり、統計開始以来、初めて1億円の大台を突破しました。この勢いはとどまることを知らず、都心3区(千代田区、中央区、港区)では中古マンションですら平均価格が1億円を超え、突出した高値圏を形成しています。
この市場の熱狂の中心にいるのが、タワーマンションです。タワーマンションに限定した価格指数を見ると、その上昇はさらに顕著で、2024年には前年比で実に+25%という驚異的な伸びを記録しました。これは市場全体の上昇率(+13%)を大きく上回るものであり、タワーマンションが価格高騰の牽引役であることを明確に示しています。ただし、この価格高騰は首都圏全体で一様ではありません。都心部が記録的な価格を更新する一方で、郊外エリアへの価格上昇の波及は緩やかであり、都心と郊外の「価格の二極化」が鮮明になっています。
逼迫の危機:歴史的な供給不足
この価格高騰を理解する上で最も重要な要素は、需要の大きさ以上に、深刻な供給不足にあります。2024年の首都圏における新築マンション供給戸数は前年比で14.4%も減少し、これは1973年の調査開始以来で最も少ない数字となりました。特に価格を牽引する東京23区に絞ると、その落ち込みはさらに激しく、供給戸数は前年比で30.5%もの激減を記録しています。
これは一時的な現象ではありません。都心部での用地取得が年々困難になっていること、コロナ禍における開発計画の遅延、そして後述する建築コストの高騰といった構造的な問題が背景にあります。デベロッパーは、限られた土地で事業採算性を確保するため、より付加価値の高い、つまり高価格な物件を少数供給する戦略を取らざるを得なくなっているのです。この供給側の制約が、現在の市場価格を高止まりさせる根本的な原因となっています。
コストプッシュの現実と需要の揺らぎ
現在の価格高騰は、需要が価格を引っ張り上げる「デマンドプル型」の側面だけでなく、コストが価格を押し上げる「コストプッシュ型」の要因も極めて大きいのが特徴です。建設物価調査会によれば、建築費指数は一貫して上昇を続けており、特に建設業界の「2024年問題」に象徴される人件費や、資材費の高騰が新築マンション価格に直接的に転嫁されています。これは価格に強力な下方硬直性をもたらし、市場価格を高止まりさせる強力な要因となっています。
興味深いことに、価格が上昇し続ける一方で、需要側の足元には揺らぎが見えます。首都圏新築マンションの初月契約率は、好不調の目安とされる70%を4年ぶりに下回り、66.9%に低下しました。これは、あまりにも急ピッチな価格上昇に一部の購入希望者が追随できなくなり、販売価格と購入希望額との間にギャップが拡大していることを示唆しています。契約率の低迷は販売在庫の増加にもつながっており、2024年末時点の在庫は2年連続で増加しました。この事実は、市場が無限の需要に支えられているわけではないことを示しています。
グローバルな影響:円安と海外投資家
さらに、マクロ経済環境、特に歴史的な円安が市場に与える影響は無視できません。海外の投資家にとって、日本の不動産、特に政治的に安定した東京のプライムアセットは、自国通貨建てで見ると相対的に「割安」に映ります。実際に、東京湾岸エリアで1億円を超えるタワーマンションの購入者を調査したところ、そのうちの3割が外国人名義であったというデータもあり、海外からの資金流入が国内の富裕層と競合し、価格を押し上げる一因となっていることは明らかです。
これらのデータを総合すると、現在のタワマン市場は、単に「高齢富裕層の相続需要」という一つのドライバーによって引き起こされた単純なバブルではないことがわかります。むしろ、「歴史的な供給不足」と「建築コストの高騰」という供給側の制約が価格を高止まりさせる中で、「パワーカップルを中心とした国内の実需・資産形成需要」と「円安を背景とした海外投資需要」がぶつかり合うことで形成された、「供給主導型の価格高騰」と表現するのがより正確な分析でしょう。需要が旺盛だから価格が上がるというよりも、供給が極端に絞られているからこそ、限られた物件に富裕な需要が集中し、価格が異常なレベルにまで押し上げられているのです。
| 指標 | 東京23区 | 神奈川県 | 埼玉県 | 千葉県 | 首都圏合計 |
| 新築平均価格 | 1億1,483万円 (2023年) | 6,968万円 (2025年3月) | 6,027万円 (2025年3月) | 4,749万円 (2025年3月) | 7,820万円 (2024年) |
| 中古平均価格 (70㎡換算) | 9,501万円 (2025年3月) | 4,585戸 (供給数) | 3,313戸 (供給数) | 4,457戸 (供給数) | 4,705万円 (2024年8月) |
| 新築供給戸数 (2024年) | 8,275戸 (-30.5%) | 4,917戸 | 3,313戸 | 4,457戸 | 23,003戸 (-14.4%) |
| 新築初月契約率 (2024年) | 68.8% | 68.0% | 61.8% | 68.7% | 66.9% (-3.4p) |
注: 各データは発表時期や調査機関により異なるため、代表的な数値を記載。カッコ内は前年比または前年同月比。
第2章:新たな主役たち:現代のタワマン購入者は誰なのか?
仮説の中心である「相続を控えた高齢富裕層」が本当に市場の主役なのでしょうか。この点を検証するため、実際の購入者データに深く切り込んでいくと、仮説とは大きく異なる、新しい購入者像が鮮明に浮かび上がってきます。市場の需要エンジンは、静かに世代交代を遂げていたのです。
拡大する富裕層という土壌
まず、仮説の前提となる富裕層人口の増加は事実です。野村総合研究所の最新の推計によれば、2023年時点で純金融資産1億円以上の「富裕層」と5億円以上の「超富裕層」を合わせた世帯数は165.3万世帯に達し、2021年から11.3%も増加しました。彼らが保有する純金融資産の総額も約469兆円と、わずか2年間で約29%も増加しており、高額不動産を購入しうるポテンシャルを持った層が社会全体で拡大していることは間違いありません。この巨大な富のプールが、高額不動産市場の土壌となっていることは事実です。
年齢のミスマッチ:主役は現役世代
しかし、この巨大な富裕層プールがそのままタワーマンション市場に流れ込んでいるわけではありません。複数の購入者調査が、驚くほど一致した結果を示しています。リクルートによる2024年の首都圏新築マンション契約者動向調査では、購入者の平均年齢は39.0歳でした。これは、相続を目前に控えた高齢者層とは明らかに異なる、キャリア形成期にある現役世代の姿です。
この傾向は、超高額物件においても同様です。例えば、三井不動産レジデンシャルが供給した「パークコート神宮北参道 ザ タワー」は、最高価格13億7,000万円という超富裕層向けの物件ですが、その購入者層で最も多かったのは50代(26%)、次いで40代(25%)であり、60歳以上は約34%にとどまります。1億円以上のマンション購入者に限定した別の調査でも、最も多い年代は40代という結果が出ており、市場の最前線を牽引しているのが、まぎれもなく30代から50代の現役世代であることが裏付けられています。
新たな富裕層「パワーカップル」の台頭
では、この現役世代の購入者は一体誰なのでしょうか。野村総合研究所は、新たな富裕層トレンドとして、都市部在住で世帯年収3,000万円以上の大企業共働き世帯、いわゆる「スーパーパワーファミリー」の増加を指摘しています。彼らは、親の世代から受け継いだ資産家ではなく、自らの高い稼得能力によって富を築く新しいタイプの富裕層です。
この分析は、不動産市場のミクロなデータによって強力に裏付けられています。ある湾岸エリアのタワーマンション購入者を対象とした登記簿調査では、実に購入者の約30%が「パワーカップル」であったことが判明しました。彼らの購買行動には明確な特徴があります。2LDKや3LDKといったファミリータイプの住戸を好み、世帯年収は平均で1,000万円を大きく超え、その多くが夫婦それぞれでローンを組む「ペアローン」を積極的に活用して、高額な物件を購入しているのです。彼らは、レバレッジを効かせて資産規模の拡大を狙う、極めて合理的な経済主体と言えます。
動機の根本的転換:「相続対策」から「資産形成」へ
購入者の動機を分析すると、古い仮説との決定的な違いがさらに鮮明になります。新築マンションの購入理由のトップは依然として「子どもや家族のため」ですが、それに肉薄する2位につけ、過去最高の割合となったのが「資産を持ちたい、資産として有利だと思ったから」(35%)という理由です。
この「資産性」を重視する傾向は、特にシングル世帯で強く見られるほか、パワーカップルも将来の資産価値を極めて重視していることが調査で明らかになっています。これは、親から子へ財産を移す「相続・資産承継」のフェーズではなく、自らの力で富を築き上げる「資産形成」フェーズにある人々のマインドセットを色濃く反映しています。彼らにとってタワーマンションは、終の棲家ではなく、自身のポートフォリオを構成する重要な「資産」なのです。
この変化が示唆するのは、タワーマンション市場がよりプロシクリカル(景気循環増幅的)で、潜在的により変動しやすくなった可能性です。相続対策を目的とした需要は、市場の上下動とは比較的無関係に安定して存在しますが、「資産形成」を目的とした需要は、将来の価格上昇への期待に強く依存します。この新しい需要層は、高いレバレッジ(ペアローンなど)を利用しているため、金利の上昇や景気後退による高所得雇用の減少といった経済ショックに対して、より脆弱である可能性も秘めています。需要の基盤は、かつてのパラダイムよりも、ある意味で脆くなっているのかもしれません。
結論として、データが示す現代のタワマン購入者の中心像は、「相続税対策に悩む高齢富裕層」ではありません。それは、「高収入を背景に、将来の資産価値を見据えて高額な住宅ローンを組む、30代・40代のパワーカップルや富裕層予備軍」なのです。市場の需要エンジンは、完全に世代交代を遂げているのです。
第3章:税制の逆襲:2024年改正はいかに「タワマン節税」を無力化したか
仮説の根幹をなしてきた「タワマン節税」。この強力なインセンティブが、2024年1月1日をもって大きくその姿を変えました。国税庁による相続税財産評価のルール改正は、まさにタワーマンションを利用した過度な節税スキームに狙いを定めたものであり、この改正内容を理解することなくして現在の市場は語れません。この改正は、古い仮説に決定的なとどめを刺す一撃となりました。
旧ルールの仕組み:時価と評価額の歪み
かつての「タワマン節税」は、不動産の「時価」と「相続税評価額」の間に存在する巨大な乖離を利用する、極めてシンプルな仕組みでした。相続税評価額は、土地については国税庁が定める路線価、建物については市町村が定める固定資産税評価額を基に算出されます。この評価額は、一般的に時価よりも大幅に低く設定されており、特にタワーマンションではその傾向が顕著でした。
例えば、同じ専有面積であれば、眺望の悪い低層階も眺望の良い高層階も、建物の固定資産税評価額に大きな差はありませんでした。しかし、市場価格は眺望に比例して高層階ほど高くなるため、都心の人気タワーマンションの高層階では、相続税評価額が時価の2〜3割程度にまで圧縮されるケースも珍しくなかったのです。1億円の現金を相続すれば1億円が課税対象となりますが、1億円でタワーマンションを購入すれば、その評価額は2,000万円や3,000万円となり、課税ベースを劇的に下げることができました。これが、富裕層にとっての強力な購入インセンティブとなっていたのです。
新ルールの解剖:乖離を狙い撃つ新評価方式
この状況を問題視した国税庁が導入したのが、2024年1月1日以降の相続・贈与から適用される新ルールです。この改正の核心は、従来の評価額に「区分所有補正率」という新たな倍率を乗じることで、評価額を時価に近づけようという試みにあります。
この補正率を算出する上で鍵となるのが「評価乖離率」という指標です。この評価乖離率は、以下の4つの要素から計算される、まさに「タワマン節税」をピンポイントで狙い撃つために設計された数式です。
- 築年数(マイナス要素): 築年数が浅い(新しい)ほど、評価額が上がる(節税効果が減る)。
- 総階数(プラス要素): 総階数が高い(高層である)ほど、評価額が上がる(節税効果が減る)。
- 所在階(プラス要素): 部屋の所在階が高いほど、評価額が上がる(節税効果が減る)。
- 敷地持分狭小度(マイナス要素): 専有面積に対する敷地権の割合が小さい(都心のタワマンに典型的)ほど、評価額が上がる(節税効果が減る)。
この数式の設計意図は一目瞭然です。時価を押し上げる要因である「新しさ」「高さ」「都心立地」といった要素が、そのまま相続税評価額をも引き上げるペナルティとして機能するよう設計されているのです。これにより、時価と評価額の間の都合の良い「歪み」は、体系的に修正されることになりました。
「6割ルール」という決定打
そして、この改正の最も重要なルールが、通称「6割ルール」です。これは、従来の方式で計算した評価額が、国税庁の算定する理論上の時価(評価乖離率の逆数から算出)の60%に満たない場合、強制的に時価の60%まで評価額が引き上げられるというものです。
このルールにより、評価額が時価の2割や3割といった極端な圧縮は事実上不可能となり、節税メリットに明確な上限が設けられました。これは、「タワマン節税」というゲームのルールを根本から変える、決定的な一撃でした。
この税制改正は、市場を分析する上での完璧な「自然実験」として機能します。もし市場が本当に相続税対策需要に支えられていたのであれば、この改正後に、特に新築・高層階のタワーマンション市場は大きな打撃を受けたはずです。しかし、現実には市場は高騰を続けました。この事実は、市場が税制改正をものともしない、より強力な別のドライバーによって動かされていることを何よりも雄弁に物語っています。つまり、税制改正は市場を殺さなかった代わりに、市場がもはや「タワマン節税」に依存していないことを証明したのです。
| 計算ステップ | 改正前(〜2023年) | 改正後(2024年〜) | 備考 |
| 前提条件 | 市場価格:2億円 | 従来の評価額:6,000万円 | 物件:築5年、35階建/32階 |
| ① 評価乖離率の計算 | 適用なし | 2.277 | 築年数、総階数、所在階、敷地持分狭小度から算出。 |
| ② 評価水準の計算 | 適用なし | 1÷2.277≈0.439 | 評価乖離率の逆数。時価に対する評価額の割合を示す。 |
| ③ 評価水準の判定 | 適用なし | 0.439<0.6 | 評価水準が0.6未満のため、評価額の引き上げ補正が適用される。 |
| ④ 補正率の計算 | 適用なし | 2.277×0.6=1.3662 | 評価水準が0.6未満の場合の計算式。 |
| ⑤ 最終的な相続税評価額 | 6,000万円 | 6,000万円×1.3662≈ 8,197万円 | 従来の評価額に補正率を乗じる。 |
| 評価額の増加 | – | +2,197万円 | 課税対象額が約36.6%増加。 |
第4章:転売市場の力学:投機熱か、戦略的売却か
仮説のもう一つの柱は、活発な転売市場の存在でした。この市場は、相続対策を目的とする最終需要家(高齢富裕層)への供給ルートとして機能している、という見立てです。しかし、転売市場の動向を詳しく分析すると、その動機はより一般的で、特定の相続ニーズに応えるという特殊な目的とは異なる、普遍的な投資ロジックに基づいていることが見えてきます。
高い転売意欲と迅速な売却
タワーマンション購入者の多くが、永住ではなく将来の売却を視野に入れていることは事実です。ある調査では、自宅用に購入した人のうち、「いずれ売却しようと思っていた」と回答した割合は45.9%にのぼり、「ずっと住もうと思っていた」の36.8%を上回りました。
そして、その売却プロセスは驚くほど速いのが特徴です。売却活動を開始してから半年以内に売買契約を完了させた人が6割近くに達します。これは、市況の良いタイミングを逃さず、迅速に利益を確定させたいという強い意図の表れです。数年から数十年単位の長期的な視野で動く相続計画とは、明らかに異なる時間軸で市場が動いていることを示唆しています。
明確な利益追求の動機
売却の最大の目的は、キャピタルゲイン(売却益)の獲得です。同調査では、売却者の6割近くが1,000万円以上の利益を得ることに成功しています。この明確な利益追求の動機は、不動産投資における普遍的な論理であり、特定の相続ニーズに応えるという特殊な目的とは一線を画します。買い手も売り手も、この市場を投資の舞台として捉えているのです。
税制が促す「中期投資」
ただし、純粋な短期転売(フリッピング)には税制上のブレーキがかかります。不動産を売却して得た利益(譲渡所得)にかかる税率は、所有期間が売却した年の1月1日時点で5年以下の場合、「短期譲渡所得」として約39.63%もの高率が課されるのに対し、5年を超えると「長期譲渡所得」として約20.315%に軽減されます。
この税制は、数ヶ月単位での投機的な転売を抑制し、少なくとも5年超の保有を促す強力なインセンティブとして機能します。これにより、タワーマンションの転売は「中期的な投資」という性格を帯びることになります。購入者は市場の上昇トレンドを確信し、税制上有利になるタイミングを見計らって売却することで、キャピタルゲインの最大化を図ります。この行動様式は、一般的な不動産投資家のそれと何ら変わるところはありません。
転売市場の本当の役割
これらの事実を総合すると、タワーマンションの転売市場は、「相続対策を計画する高齢富裕層への供給パイプライン」として特化しているわけではないことがわかります。むしろ、それは「一般的な価格上昇期待を背景とした、投資家による利益確定の場」として機能しているのです。
この転売市場の存在は、一次市場(新築市場)の「資産形成」という物語を裏付け、増幅させる重要な役割を担っています。新築マンションの購入を検討しているパワーカップルが、数年前に購入した人々が転売によって多額の利益を得ているという事実を目にすれば、それは「タワーマンションは儲かる資産である」という強力な証拠(プルーフ・オブ・コンセプト)となります。この成功事例が、新たな買い手を市場に呼び込み、彼らがまた数年後に利益確定の売り手となる。このサイクルが、市場の熱狂を自己増殖させているのです。
したがって、転売市場は相続需要仮説の結果として存在するのではなく、価格高騰という現象そのものを増幅させるアンプリファイア(増幅器)として、バブルの熱狂をさらに加速させる役割を担っていると結論付けられます。
第5章:仮説への審判:より複雑で進化する真実
これまで多角的に行ってきた分析を統合し、「高齢富裕層の相続対策需要がタワマンバブルを牽引している」という長らく信じられてきた仮説に、最終的な審判を下します。結論から言えば、この仮説は、かつて市場の一側面を的確に捉えていたかもしれませんが、現在の、そして未来のタワーマンション市場を動かす主たる原動力ではありません。物語は完全に書き換えられたのです。
仮説の終焉を告げた決定打
この仮説が過去のものとなった最大の要因は、2024年の相続税評価額に関する税制改正です。この改正は、タワーマンション、特に新築・高層階の物件が持つ税制上のアービトラージ(裁定取引)機会を直接的かつ効果的に潰すものでした。時価と評価額の乖離を強制的に是正する新ルールは、仮説の根幹をなす「タワマン節税」というインセンティブを大幅に削ぎ落としました。これにより、相続対策を主目的として新たに高額なタワーマンションを購入するという行動の合理性は、著しく低下したのです。
市場の新たなパラダイム:主役交代と構造変化
では、古い仮説に代わる、現在の市場を動かす真のドライバーは何なのでしょうか。それは単一の要因ではなく、以下の4つの力が複合的に作用した、より複雑なパラダイムです。
- 国内の新世代富裕層の台頭: 市場の需要エンジンは、相続を考える高齢者から、自らの資産形成期にある30代〜50代の「パワーカップル」や富裕層予備軍へと明確にシフトしました。彼らにとってタワーマンションは、節税商品ではなく、ポートフォリオの中核をなす「資産」であり、将来のキャピタルゲインを期待した投資対象です。
- 供給とコストの構造的制約: 都心部における用地取得の困難化と、高騰し続ける建築コストが、慢性的な供給不足を生み出しています。これにより、新築物件の価格には高い下限が設定され、希少な供給に対して、価格感応度の低い富裕な需要が集中する構造が定着しました。
- グローバル資本の流入: 歴史的な円安は、日本のプライムアセットを海外投資家にとって魅力的な投資先に変えました。彼らの旺盛な需要は、国内の需要層と競合し、価格をさらに押し上げる圧力となっています。
- インフレヘッジとしての不動産: 世界的なインフレ環境下で、実物資産である不動産、特に政治的に安定した国の主要都市にあるプライム物件は、価値の保存手段(インフレヘッジ)として見直されています。このグローバルな資金の流れが、東京のタワーマンション市場にも恩恵をもたらしているのです。
結論:物語の書き換え
要するに、タワーマンションを巡る物語は完全に書き換えられました。かつての主役は「相続財産を圧縮したい日本の高齢富裕層」だったかもしれません。しかし、現在の物語の主役は、「インフレと世界経済の変動の中で、希少なプライムアセットを巡って、グローバル資本と競争する日本の新世代富裕層」なのです。バブルの様相を呈する市場の熱狂は、この新たな、そしてよりダイナミックな競争の構図から生まれています。
第6章:見えざる氷山:未来のリスクと真の長期的課題
市場価格の「バブル」を巡る議論は、しばしば価格そのものの変動に終始しがちです。しかし、タワーマンションという資産形態が内包する、より構造的で長期的なリスクを見過ごしてはなりません。それこそが、購入者や所有者が直面する「見えざる氷山」であり、その価値を将来にわたって左右する真の課題です。
忍び寄る維持管理の危機:「修繕積立金」問題
タワーマンションが抱える最大の時限爆弾、それは修繕積立金の不足問題です。多くのタワーマンションは、分譲時の販売促進のために、当初の修繕積立金を意図的に低く設定しています。しかし、タワーマンションは外壁の特殊な足場、高性能なエレベーター、豪華な共用施設など、一般のマンションとは比較にならないほど大規模かつ高コストな修繕を将来的に必要とします。
この危機的状況に対し、国土交通省は2021年に「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」を10年ぶりに改定しました。ここで示された目安額は衝撃的なものでした。特に20階建て以上のタワーマンションにおける修繕積立金の目安(中心値)は、1平方メートルあたり月額206円から338円へと、実に64%もの大幅な引き上げとなったのです。これは、将来的に多くのタワーマンションで、現在の積立金が数倍に跳ね上がる可能性を示唆しています。この不可避なコスト増は、所有者の家計を圧迫し、支払えない世帯の出現や、売却時の価格競争力を削ぐ深刻な要因となりえます。
ガバナンスの悪夢:「管理組合」問題
第二のリスクは、人間関係と意思決定の困難さ、すなわち管理組合の機能不全です。数百、時には千を超える世帯が一つの建物を共有するタワーマンションにおいて、合意形成は極めて困難を極めます。
その背景には、所有者の多様性があります。永住を目的とする居住者、賃貸に出して収益を得たい国内投資家、節税や資産価値の維持にしか関心のない不在地主、そして連絡すら困難な海外投資家。それぞれの利害は複雑に対立し、「自分は利用しない共用施設の修繕」や「大幅な積立金の値上げ」といった重要議案に対して、可決に必要な特別多数(通常4分の3)の賛成を得ることは至難の業です。実際に、理事会と所有者の対立や、いわゆる「カスハラ」によって管理会社が業務から撤退してしまうという深刻な事例も報告されています。
このガバナンスリスクは、現代の購入者プロファイルによって、さらに悪化する可能性があります。中期的な資産形成を目的とするパワーカップルや、そもそも居住していない国内外の投資家は、時間と労力がかかる管理組合の運営に積極的に関与するインセンティブが低い傾向にあります。30年後の建物の健全性のために現在の積立金を倍にする、という議案に対し、7年後の売却益を最大化したい所有者は「ノー」と投票する合理的な理由を持ってしまうのです。これは、個人の短期的な利益が、共同体の長期的な利益と衝突する「共有地の悲劇」そのものです。
「スラム化」という最悪のシナリオと、ガバナンスの力
これら二つのリスクは密接に連動しています。管理組合の機能不全は、修繕積立金の値上げ決議の失敗を招きます。資金がなければ、計画的な大規模修繕は実行できません。その結果、建物の物理的な劣化(雨漏り、設備の故障など)が進行し、資産価値は回復不可能なまでに毀損していく。これが、一部の専門家が警鐘を鳴らすタワーマンションの「スラム化」への道筋です。
一方で、この危機を乗り越えることに成功した事例も存在します。強力なリーダーシップを持つ理事会が、住民への丁寧な説明を重ねて積立金の3倍増額を実現したケースや、積立金を国債などで賢く運用し、15年間で2億4,000万円もの利益を生み出した武蔵小杉のタワーマンションの事例は、その好例です。
これらの事例が示すのは、タワーマンションの長期的な資産価値を決定づけるのは、分譲時の価格や立地といった初期条件だけではない、ということです。むしろ、竣工後にそのマンションのコミュニティが培っていく「管理の実力」こそが、将来の価値を左右する最も重要な変数なのです。市場の熱狂に目を奪われることなく、この足元のリスクを直視し、優れたガバナンスを構築できるかどうかが、すべてのタワーマンション所有者に突きつけられた、真の課題と言えるでしょう。