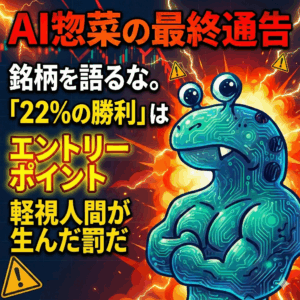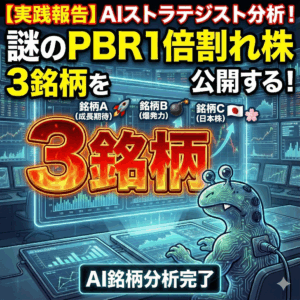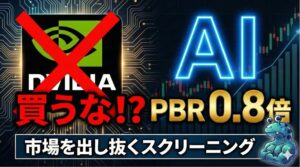固定電話の回線廃止の影響って結構あるみたいですね。

序論:一世代に一度のインフラ大変革
エグゼクティブ・サマリー
本レポートは、日本電信電話株式会社(以下、NTT)が2035年までに固定電話用の銅線(メタル回線)を廃止するという決定が、日本の通信インフラ市場に与える構造的変化と、それに伴う投資機会を分析するものである。この決定は、単なる技術の旧式化への対応にとどまらず、数兆円規模の投資を促す長期的な触媒(カタリスト)として機能する。銅線の撤去と光ファイバー網への移行は、今後10年間にわたり、通信建設、光ファイバー製造、ネットワーク機器、さらには通信サービス市場に至るまで、特定の産業分野に予測可能かつ持続的な追い風をもたらす。本分析では、この巨大な代替需要の恩恵を直接的・間接的に受ける上場企業を特定し、その選定理由を事業内容、財務状況、市場での競争優位性に基づき詳細に解説する。投資戦略としては、インフラ構築を担う「通信建設会社」、基盤材料を供給する「光ファイバー・部品メーカー」、新ネットワークの頭脳となる「ネットワーク機器・ゲートウェイプロバイダー」、そして顧客獲得競争を繰り広げる「代替サービス事業者」という4つの主要カテゴリーに着目し、それぞれのリスク・リターン特性に応じた投資対象を提示する。
カタリスト詳解
2025年8月6日、NTTは固定電話サービスに使用している銅回線を2035年までに廃止する方針を正式に表明した。この発表は、日本の通信インフラにおける歴史的な転換点の到来を告げるものである。
- 「何を」: NTTは、2035年を目途に、固定電話サービスで使用されている銅線(メタル回線)を段階的に廃止する。
- 「なぜ」: この決定の背景には、二つの大きな圧力がある。第一に、敷設から数十年が経過した銅線網の「設備の老朽化」である。第二に、携帯電話の普及に伴う固定電話契約数の激減である。契約数は1997年のピーク時6322万件から、2025年6月には1130万件まで減少し、今後もこの傾向は続くと見込まれている。この結果、利用率の低いインフラの「維持負担がかさんでおり」、経済合理性が失われている。
- 「どのように」: 廃止される銅線網の代替手段として、主に「光回線」および携帯電話の電波を利用した「固定無線アクセス(FWA)」サービスへの移行が進められる。NTTの島田明社長は、利用者に不便が生じないよう、十分な周知期間と移行期間を設けると言明しており、具体的な移行計画はNTT東日本・西日本から9月下旬に公表される予定である。
- 「いつ」: 2025年から2035年までの明確な10年間のタイムラインが設定された。この長期的かつ公式に表明された国家規模のプロジェクトは、投資家にとって異例なほどの事業予測の透明性を提供する。
経済合理性:運用コストから設備投資への転換
NTTのこの決定を深く理解する上で重要なのは、これが単なる技術更新ではなく、根本的な経済的判断であるという点だ。老朽化し、利用者も減少している銅線網を維持するために発生する莫大な運用コスト(OpEx)を、将来性があり効率的なオールIPネットワークへの設備投資(CapEx)へと振り向けるという、戦略的な財務判断が根底にある。
NTTの島田社長は、特に災害の多い九州地方などを例に挙げ、メタル回線の維持には多大な工夫が必要であり、今後新たにメタル回線を敷設することは非効率的であると述べている。これは、維持・補修費用が事業を圧迫している現状を示唆している。つまり、これから始まる大規模な光化プロジェクトの原資は、単なる「成長投資」としての新規予算だけでなく、これまで銅線網の維持に費やされてきた年間数千億円規模の「維持管理費」の再配分によって、その多くが賄われる可能性が高い。
この財務的な必然性は、プロジェクトの実行確度を極めて高いものにしている。景気の短期的な変動に左右されにくく、移行に関与する企業にとっては、安定的かつ長期的な収益源が確保されることを意味する。これは、政府の暗黙の支持を得た国家規模のインフラ更新プロジェクトであり、その中心には強固な経済的動機が存在するのである。
第1章 技術シフト:アナログからオールIPへ
レガシーネットワーク(PSTN/ISDN)の解体
今回の物理的な銅線廃止は、2024年1月に実施されたPSTN(公衆交換電話網)のIP網への移行とは本質的に異なる。2024年の移行は、NTT局内の交換機をIPベースのルーターに置き換えるものであり、利用者宅から局舎までの「ラストワンマイル」の銅線はそのまま利用された。これは言わば「舞台裏」の論理的なネットワーク変更であり、利用者は手続きや工事不要で従来の電話機を使い続けることができた。
しかし、2035年までの計画は、このラストワンマイルの物理的な銅線そのものを光ファイバー等に置き換える、より大規模なインフラ更新である。これにより、長年日本の通信を支えてきたISDN(総合デジタル通信サービス)も、その役割を完全に終えることになる。「INSネット ディジタル通信モード」は2024年1月にすでに終了しており、サービス自体も2028年末に提供を終える予定だ。
後継技術:多層的なエコシステム
NTTが創出する「代替需要」は一枚岩ではない。それは、品質、利便性、コストに応じて階層化されたソリューションによって満たされることになる。
- 主要な代替手段 – FTTH & 光電話:これは代替の「ゴールドスタンダード」であり、光ファイバーケーブルを各家庭まで引き込むことで通信サービスを提供する。
- 特徴: 音声データを光信号に変換して伝送するため、他のIP電話に比べて音声品質が極めて高く、安定的かつセキュアである。従来の固定電話と同じ市外局番から始まる「0AB-J番号」を引き継ぐことができ、110番や119番といった緊急通報にも対応しているため、真の意味で従来の固定電話の代替となり得る。広義にはIP電話の一種だが、専用の管理された光ネットワークを利用する点で、インターネット上をデータが流れる一般的なIP電話(050電話)とは区別される。
- 重要な代替手段 – 固定無線アクセス(FWA):これは、5Gなどの携帯電話ネットワークの電波を利用して、家庭向けのインターネット接続や音声通話サービスを提供する技術である。
- 特徴: 最大の利点は、物理的な回線引き込み工事が不要である点(「工事不要」)。従来、FWAは光ファイバーの敷設が困難な山間部や離島向けの補完的な技術と見なされてきた。しかし、ローカル5Gなどを活用した現代のFWAサービスは、高速・大容量通信を実現し、光ファイバーの有力な代替選択肢として積極的に位置づけられている。
- 必須となるハードウェア – VoIPゲートウェイ & ルーター:IPネットワークへの移行に伴い、すべての利用者は新たな宅内機器(CPE)を必要とする。
- 機能: VoIPゲートウェイ(またはVoIP機能内蔵のホームゲートウェイ)は、従来のアナログ電話機からの音声をIPパケットに変換し、IP網上で通話できるようにする装置である。また、高速な光回線の性能を最大限に引き出すためには、高性能なルーターが不可欠となる。
三つの異なる市場機会の出現
この技術移行は、性質の異なる三つの市場を同時に生み出す。これらを個別に理解することが、的確な投資戦略の鍵となる。
- 高品質・大規模なFTTH敷設市場: これは、数百万世帯に及ぶ光ファイバーの敷設という、物理的な労働力と資材を大量に必要とする市場である。この分野では、インフラ工事を担う通信建設会社や、光ファイバーケーブルを製造するメーカーが主役となる。
- 破壊的・高成長のFWA市場: こちらは、物理的な工事を嫌う層や、迅速な開通を求める層を取り込む、利便性を武器とした市場である。5G基地局の整備や高性能な5G対応ホームルーターの開発・提供が成功の鍵を握り、先進的な無線技術を持つ通信事業者や機器メーカーに機会をもたらす。
- 膨大なCPE(宅内機器)の交換市場: FTTHへ移行するにせよ、FWAを選択するにせよ、最終的に約1130万件の契約者は、IPネットワークに対応した新しいゲートウェイやルーターを家庭に設置する必要がある。これは、特定のハードウェアに対する巨大なボリュームの買い替え需要を生み出す。
したがって、洗練された投資戦略は、これら三つの異なる機会(大規模インフラ、破壊的技術、大量生産ハードウェア)に資本を分散させ、それぞれのリスク・リターン特性を考慮する必要がある。
旧世代および次世代固定電話技術の比較
- アナログ電話 (PSTN)
- 基盤ネットワーク: 銅線(公衆交換電話網)
- 代表的な通話品質: 安定
- データ通信速度: 低速(モデム)
- 緊急通報(110/119): 対応
- 番号ポータビリティ(0AB-J): 対応
- 回線工事: 必要
- ISDN
- 基盤ネットワーク: 銅線(デジタル網)
- 代表的な通話品質: 高品質・安定
- データ通信速度: 64kbps/128kbps
- 緊急通報(110/119): 対応
- 番号ポータビリティ(0AB-J): 対応
- 回線工事: 必要
- IP電話 (050)
- 基盤ネットワーク: インターネット(ベストエフォート)
- 代表的な通話品質: 不安定な場合あり
- データ通信速度: ブロードバンド
- 緊急通報(110/119): 非対応の場合が多い
- 番号ポータビリティ(0AB-J): 不可(050番号)
- 回線工事: 不要
- 光電話 (FTTH)
- 基盤ネットワーク: 光ファイバー(専用IP網)
- 代表的な通話品質: 非常に高品質・安定
- データ通信速度: 超高速(1Gbps以上)
- 緊急通報(110/119): 対応
- 番号ポータビリティ(0AB-J): 対応
- 回線工事: 必要
- 5G FWA
- 基盤ネットワーク: 5G/モバイル網
- 代表的な通話品質: 高品質(電波状況による)
- データ通信速度: 高速(数百Mbps~Gbps級)
- 緊急通報(110/119): 対応(サービスによる)
- 番号ポータビリティ(0AB-J): 対応(サービスによる)
- 回線工事: 不要
この比較は、なぜ技術移行が必要なのか、そして代替選択肢の間にどのようなトレードオフが存在するのかを視覚的に示しており、後続の企業分析の前提となる重要な文脈を提供する。
第2章 「ツルハシとシャベル」戦略:通信建設・エンジニアリング業界
市場概観
NTTの銅線廃止から最も直接的かつ巨大な恩恵を受けるのが、通信建設業界である。数百万回線に及ぶ銅線を物理的に光ファイバーへ置き換える作業は、壮大な土木・電気通信工事であり、今後10年間にわたる安定した事業機会を創出する。この市場は、NTTと長年にわたる深い関係を築いてきた少数の大手企業によって寡占されている。一部の通信キャリアによる設備投資抑制の動きがある中でも、情報通信設備工事大手3社は旺盛な需要を背景に受注を伸ばしており、このプロジェクトが強力な下支えとなることが確認されている。
主要企業分析:「ビッグスリー」
- コムシスホールディングス (証券コード: 1721.T)
- 市場での位置づけ: 通信設備工事で国内首位を誇る業界のリーダーである。特にNTTグループとの関係は極めて深く、売上高の約4~5割をNTT設備事業が占める。この高いNTT依存度は、今回のプロジェクトにおいて、同社が最大の受益者の一人であることを明確に示している。事業ポートフォリオは、通信キャリア事業を中核に、ITソリューション、社会システム関連事業へと多角化している。
- 財務・業績: 近年の業績は好調で、特に利益面で大きな伸長を見せている。増配を予定するなど株主還元にも積極的であり、安定した財務基盤を持つ。同社の月次受注状況は、プロジェクトの進捗を測る上で重要な指標となるだろう。
- エクシオグループ (証券コード: 1951.T)
- 市場での位置づけ: コムシスHDと並ぶ業界大手の一角。中核の通信キャリア事業に加え、都市インフラ事業やシステムソリューション事業など、幅広い事業ポートフォリオを持つ。この多角化は、特定の事業への依存度を下げ、経営の安定性に寄与する一方、NTTの光化プロジェクトへの直接的なレバレッジ(てこの原理)はコムシスHDに比べてやや小さい可能性がある。
- 財務・業績: 12期連続の増配を予定するなど、株主還元への強いコミットメントを示している。株価は市場の期待を反映して堅調に推移しており、8月8日に予定されている第1四半期決算が今後の動向を占う上で注目される。
- 株式会社ミライト・ワン (証券コード: 1417.T)
- 市場での位置づけ: 複数の大手通信建設会社が経営統合して誕生した業界第3位の企業。近年は非キャリア事業や「みらいドメイン」と称する新領域への戦略的シフトを加速させており、これらの事業が売上高の過半を占めるに至っている。
- 財務・業績: 2026年3月期に向けて大幅な増収増益を見込んでおり、増配も計画している。株価も好調に推移している。投資家にとっての論点は、同社がこの伝統的なNTTアクセス網工事にどれだけ経営資源を配分するか、そして新成長領域である「みらいドメイン」とのシナジーをいかに生み出していくかという点にある。
「確実性プレミアム」と競争優位性
この「ビッグスリー」が享受する最大の強みは、この国家規模のプロジェクトにおける、他社の追随を許さない強固な競争優位性(Competitive Moat)である。これは単なる施工技術の高さに起因するものではない。NTTの交換局やマンホール、さらには個人宅の敷地内での作業を伴うこの種の工事は、最高レベルのセキュリティと信頼性が要求される。
ビッグスリーは、数十年にわたりNTTと共に日本の通信インフラを構築してきた歴史を持ち、その業務プロセス、安全基準、人員はNTTのそれと深く結びついている。新規参入企業が、この特殊なノウハウと信頼関係、そして全国規模の展開に必要な動員力を短期間で構築することは事実上不可能である。
したがって、この10年間のプロジェクトから得られる収益は、単に予測可能であるだけでなく、競争から高度に保護されていると言える。この収益の「確実性」は、一般的な建設会社(その受注は景気や個別案件の動向に左右されやすい)と比較して、ビッグスリーの株価にプレミアムが上乗せされるべき根拠となる。投資判断の焦点は、「彼らが仕事を得られるかどうか」ではなく、「3社のうち、どの企業がバリュエーション、実行能力、株主還元の観点から最も魅力的な組み合わせを提供しているか」という点に絞られる。
主要通信建設会社の財務・事業指標比較
- コムシスホールディングス (1721.T)
- 時価総額: 約 9,400億円
- 売上高: 6,200億円 (25/3期予)
- 営業利益率: 7.4% (25/3期予)
- PER(株価収益率): 約 11.8倍
- 配当利回り: 約 3.3%
- NTT事業依存度: 高
- エクシオグループ (1951.T)
- 時価総額: 約 4,300億円
- 売上高: 5,608億円 (20/3期実)
- 営業利益率: 5.8% (23/3期実)
- PER(株価収益率): 約 10.5倍
- 配当利回り: 約 2.9%
- NTT事業依存度: 中~高
- ミライト・ワン (1417.T)
- 時価総額: 約 3,600億円
- 売上高: 6,200億円 (26/3期予)
- 営業利益率: 5.5% (26/3期予)
- PER(株価収益率): 約 11.5倍
- 配当利回り: 約 2.9%
- NTT事業依存度: 中
注:時価総額、PER、配当利回りは2025年8月6日時点の株価と各社公表資料に基づき算出。売上高・営業利益率は各出典に基づく。NTT事業依存度は定性評価。
第3章 基盤となるマテリアル:光ファイバー・部品メーカー
市場概観
NTTの光化プロジェクトは、物理的な光ファイバーケーブルに対する巨大かつ持続的な国内需要を生み出す。この国内需要の急増は、5Gの普及、データセンター建設、そして米国におけるBEADプログラム(ブロードバンドの公平性、アクセス、展開に関するプログラム)のような政府主導のブロードバンド整備計画に牽引される世界的なブームと時を同じくして発生している。アナリストレポートは、世界の光ファイバー市場が2030年代初頭までに170億~190億ドル規模に達すると予測しており、年平均成長率(CAGR)も10%前後と高い成長が見込まれている。日本は光ファイバー製品の主要な輸出国の一つであり、国内メーカーは世界的な競争力を有している。
主要企業分析
- 住友電気工業 (証券コード: 5802.T)
- 市場での位置づけ: 光ファイバー市場における世界的な巨人。データセンターや最先端の通信ネットワークに不可欠な、低損失ファイバーや高密度ケーブルといった高付加価値製品群に強みを持つ。同社の製品ラインナップは、幹線系から加入者宅への引き込み用まで幅広くカバーしている。
- 財務・業績: 同社の情報通信事業は、AI関連のデータセンター需要を追い風に爆発的な成長を遂げている。第1四半期決算では、情報通信関連事業の営業利益が前年同期比255.8%増という驚異的な伸びを記録した。NTTのプロジェクトは、このグローバルな高成長事業に対し、安定的かつ長期的な国内需要の基盤を提供する。アナリストによるレーティングも高く、目標株価の引き上げが相次いでいる。
- 古河電気工業 (証券コード: 5801.T)
- 市場での位置づけ: 住友電工と並ぶ世界的な大手メーカー。光ファイバー素線からネットワークシステム全体に至るまで、包括的な製品ポートフォリオを有する。特に北米市場に注力しており、米国のBEADプログラムからの需要獲得を目指すなど、グローバルな事業展開に積極的である。
- 財務・業績: 情報通信ソリューション事業は、米州における顧客の在庫調整の影響で一時的に落ち込んだが、回復が見込まれている。会社は2025年3月期に同セグメントの黒字転換を計画しており、市場の期待を反映して株価は急騰している。NTTの銅線廃止のニュースは、この回復ストーリーをさらに後押しする材料となる。
AI・データセンターという相乗効果
これら光ファイバーメーカーへの投資妙味は、NTTのプロジェクトが、AI(人工知能)を原動力とする世界的なデータセンター建設ブームと同時に進行しているという事実によって、著しく増幅される。彼らは単に古い電話線を置き換えるための部材を供給するだけでなく、次世代コンピューティングの根幹をなす「動脈」を供給しているのである。
当初の投資仮説は「NTTが光化を進めるため、住友電工や古河電工の光ファイバーが売れる」という単純なものだった。しかし、両社のIR資料を深く読み解くと、現在の彼らの成長を牽引している最大のドライバーは、データセンターからの飽くなき需要であることがわかる。AIモデルの学習や運用には、膨大なデータを高速かつ低遅延で伝送するネットワークが不可欠であり、その構築には、FTTHの敷設に使われるものと同じ、あるいはそれ以上の高性能な光ファイバーが用いられる。
したがって、NTTのプロジェクトは、今後10年間にわたる安定的で予測可能な「ベースロード」としての需要を形成する。その上で、AI・データセンター市場が、高マージンかつ爆発的な「トップライン」の成長をもたらす。この「デュアルエンジン」による成長ストーリーは、これらの企業を、単一のカタリストに依存する企業よりもはるかに魅力的な投資対象としている。
第4章 ネットワークの頭脳:機器・ゲートウェイプロバイダー
市場概観
移行される全ての回線には、新しいハードウェアが必要となる。本章では、家庭や事業所に設置されるルーター、スイッチ、そしてVoIPゲートウェイを製造する企業に焦点を当てる。日本の企業向けネットワーク機器市場は、2023年時点で3633億円を超える巨大な市場であり、今回の移行はこの市場内で大規模なハードウェア交換サイクルを引き起こす。1130万回線という膨大な数の宅内機器が、今後10年でリプレースされることになる。
主要企業分析
- 日本電気 (NEC) (証券コード: 6701.T)
- 市場での位置づけ: 日本のテクノロジー業界を代表する巨大企業であり、ネットワークインフラを含む幅広い製品・サービスにおいてNTTの主要な戦略的パートナーである。事業が多岐にわたるため、銅線廃止プロジェクトのインパクトを単体で切り出すことは困難だが、ネットワークシステムやインテグレーションサービスの中核サプライヤーとして、恩恵を受けることは確実視される。同社のIR資料は膨大であり、関連事業部門を特定するには詳細な分析が必要となる。
- ヤマハ (証券コード: 7951.T)
- 市場での位置づけ: 主に楽器で知られるが、ネットワーク機器の分野、特にSOHO(小規模オフィス・ホームオフィス)や法人向けの高性能ルーター市場で絶大な評価を得ている。その品質と性能の高さから、ギガビット級の光サービスに求められる高性能ホームゲートウェイの供給元として有力な候補である。さらに、VoIPゲートウェイのメーカーとしてもトップクラスにランク付けされており、この移行に不可欠な技術を有している。
- 財務・業績: 同社のICT事業を含むセグメントは、半導体不足の影響を受けてきたが、回復が期待されている。今回の移行は、同事業にとって大きな追い風となる可能性がある。
- 沖電気工業 (OKI) (証券コード: 6703.T)
- 市場での位置づけ: 大手企業の名声はないものの、この分野で極めて重要な役割を果たす企業である。調査によると、OKIはソフトバンクの光電話サービス「おとく光電話」向けにVoIPゲートウェイを供給している実績がある。これは決定的な証拠であり、同社が日本の大手通信キャリアに対して、キャリアグレードのVoIPハードウェアを供給できる、信頼されたサプライヤーであることを示している。また、VoIPゲートウェイメーカーとしても主要企業の一つとして認識されている。
ボリュームゲームにおける「隠れたチャンピオン」
NECのような巨大企業が有力候補であることは間違いないが、より専門性の高い沖電気工業のような企業の方が、投資の観点からは大きなレバレッジを提供しうる。需要の中心は、数百万台規模で供給される標準化されたVoIPゲートウェイであり、これは典型的な「ボリュームゲーム(数量勝負)」である。このような市場では、大規模な契約を獲得することが、企業の業績を根底から変える可能性がある。
その論理は以下の通りである。まず、約1100万台の宅内機器の交換需要が存在する。NTTのようなキャリアは、信頼できる数社のサプライヤーを選定し、大規模な発注を行う可能性が高い。ここで、沖電気工業が既にソフトバンクという大手キャリアに同種の製品を供給しているという実績は、NTTのサプライヤー選定においても極めて有利に働くことを示唆している。
この契約がNECのような巨大企業の売上高に与える影響は比較的小さいかもしれない。しかし、沖電気工業の企業規模にとって、数百万台単位の受注は、その財務状況と株価に非常に大きなインパクトを与える可能性がある。このため、沖電気工業は、この技術移行における「隠れたチャンピオン(Hidden Champion)」となるポテンシャルを秘めている。
第5章 競争の舞台:代替サービス事業者への影響
市場概観
全国規模での技術移行は、顧客の乗り換え(チャーン)を促す稀有で強力な触媒となる。NTTの競合他社は、この機会を捉え、銅線からの移行を検討している顧客に対し、単にNTT内で技術を乗り換えるのではなく、自社サービスへ乗り換えるよう、積極的なマーケティングキャンペーンを展開するだろう。これは、日本の固定ブロードバンド市場のシェアを塗り替える可能性を秘めた、10年に一度の顧客争奪戦の幕開けを意味する。
主要競合の分析
- KDDI (証券コード: 9433.T)
- 戦略: KDDIは、強力なFTTHブランド「auひかり」を武器に攻勢をかける。多くのエリアで自社独自の光ファイバー網を利用しており、高速かつ安定した通信を強みとしている。FTTH契約数はすでに約560万回線に達しており、携帯電話サービス「au」や「UQ mobile」とのセット割引(「auスマートバリュー」など)を組み合わせることで、顧客基盤のさらなる拡大とARPU(1ユーザーあたりの平均収益)の向上を目指す明確な戦略を持つ。
- ソフトバンク (証券コード: 9434.T)
- 戦略: ソフトバンクは二方面作戦を展開する。一つは「ソフトバンク光」で、これはNTTの光回線を借り受けて自社サービスとして提供する「光コラボレーション」モデルである。既存のNTTフレッツ光ユーザーにとっては、工事不要で容易に乗り換えが可能という利点がある。もう一つの強力な武器が、ソニーグループが運営する「NURO光」である。これはNTTの未使用の光ファイバー(ダークファイバー)を活用し、他社を圧倒する最大2Gbpsの超高速通信を提供することで、品質を重視するユーザー層から高い支持を得ている。
- ソニーグループ (証券コード: 6758.T) – 破壊的イノベーター
- 戦略: この競争環境において最も破壊的な存在となりうるのが、ソニーグループのソニーワイヤレスコミュニケーションズが提供する「NURO Wireless 5G」である。これはローカル5Gの免許を活用した高性能なFWAサービスであり、その最大の価値提案は「工事不要」という利便性にある。光回線と同水準の月額料金で高速通信を提供し、回線工事の手間を嫌うユーザー層をターゲットにしている。これは単なる補完サービスではなく、光ファイバーの直接的な競合として、固定ブロードバンド市場の常識を覆すことを目指している。「コンペティターはすべての通信事業者」という同社の姿勢が、その野心を示している。
FWAの真価を問うリトマス試験紙
NTTの銅線廃止は、5G FWAが日本において固定ブロードバンドの主流な代替手段となり得るか否かを占う、史上初の大規模な市場テストとして機能するだろう。
何百万人もの消費者が、長年使い続けてきた自宅のインターネットについて、初めて能動的な選択を迫られる。彼らの前には、主に二つの選択肢が提示される。一つは、工事業者の訪問を調整して物理的な光ファイバーを設置する「FTTH」。もう一つは、送られてきた箱をコンセントに差し込むだけの「FWA」である。
この移行期間中に、「NURO Wireless 5G」のようなFWAサービスが、「auひかり」やNTT自身の光サービスといった従来のFTTHサービスに対してどれだけの市場シェアを獲得できるか。その結果は、この新しい技術に対する消費者の真の評価を明確に示すことになる。もしFWAが大きな成功を収めれば、それはすべての通信事業者の長期的な設備投資計画に影響を与え、物理的な光ファイバー敷設(通信建設会社やファイバーメーカーの市場)の総需要を減少させる可能性がある。この意味で、ソニーのFWA事業の成否は、このエコシステム全体の将来を占う重要な先行指標となる。
第6章 総合分析、リスク評価、最終提言
主要な分析結果の要約
本レポートで分析したように、NTTによる2035年までの銅線網廃止は、単一の事象ではなく、連鎖的な需要を創出する多層的な投資機会である。この決定は、まず通信建設会社に10年間の安定した大規模工事需要をもたらす。次に、その工事に不可欠な光ファイバーケーブルを製造するメーカーに恩恵が及ぶ。さらに、移行する全回線で必要となるルーターやVoIPゲートウェイといった宅内機器の巨大な交換市場が生まれる。そして最後に、この大規模な顧客移行は、NTTの競合通信事業者にとって、シェアを拡大する絶好の機会となる。これらの機会はそれぞれ異なるリスク・リターン特性を持ち、投資家は自らの戦略に応じて最適な投資対象を選択することが可能である。
包括的なリスク評価
- プロジェクト実行リスク: NTTの移行スケジュールに遅延が生じたり、設備投資予算が下方修正されたりした場合、通信建設会社やサプライヤーの収益成長が鈍化する可能性がある。
- 競争・マージンリスク: 通信建設「ビッグスリー」間や、ネットワーク機器ベンダー間での価格競争が激化すれば、売上高が伸びても利益率が圧迫されるリスクがある。
- 技術的破壊リスク: 最大のリスクは、FWAの想定以上のアウトパフォームである。もしFWAが移行顧客の予想を大幅に超えるシェアを獲得した場合、新規の光ファイバー敷設需要(建設会社やファイバーメーカーに恩恵)はそれに応じて減少し、これらの企業の長期的な収益見通しに影響を与える可能性がある。
- 規制・政治リスク: 政府の通信インフラに関する政策や規制が変更された場合、プロジェクトの範囲や経済性が変わる可能性がある。
最終提言とポートフォリオ戦略
以上の分析を踏まえ、投資プロファイル別に分類した、最も魅力的な投資機会を以下に提示する。
推奨銘柄と投資テーマの要約
- コア保有(安定・確実性)
- 銘柄: コムシスホールディングス (1721.T)
- 投資テーマ: プロジェクトの中核である土木・通信工事において、業界首位として最も高い確実性と直接的な恩恵を享受。NTTとの強固な関係が揺るぎない競争優位性を構築。
- セクター成長(グローバル)
- 銘柄: 住友電気工業 (5802.T)
- 投資テーマ: 安定的なNTTの国内需要に加え、AI・データセンターという世界的なメガトレンドの恩恵を同時に受ける。デュアルエンジンによる持続的な成長が期待される。
- ニッチ・バリュー(隠れた勝者)
- 銘柄: 沖電気工業 (6703.T)
- 投資テーマ: 大手通信キャリアへの納入実績を持つVoIPゲートウェイの専門メーカー。数百万台規模の宅内機器交換サイクルにおいて、大規模契約を獲得する可能性を秘めた「隠れたチャンピオン」。
- 破壊的成長(高リスク・高リターン)
- 銘柄: ソニーグループ (6758.T)
- 投資テーマ: 5G FWAサービス「NURO Wireless 5G」を通じて、日本の固定ブロードバンド市場全体を破壊する可能性に賭ける。成功すれば大きなリターンが期待できるが、不確実性も高い。
このフレームワークは、投資家が自身のリスク許容度に応じて、この一世代に一度のインフラ変革から利益を得るためのポートフォリオを構築する上での指針となることを目指すものである。
第7章 グロース市場における新星たち
プライム市場の大手企業が安定したリターンを提供する一方で、より高い成長ポテンシャルを秘めているのがグロース市場の銘柄群である。NTTの銅線廃止は、特定の技術領域に特化した革新的な企業にとって、飛躍的な成長を遂げるまたとない機会となる。ここでは、この巨大なインフラ変革の波に乗り、大きな成長が期待されるグロース市場の注目銘柄をいくつか選定し、その理由を解説する。
ベイシス (4068.T) – 現場を支えるインフラテックの雄
- 事業内容: 携帯電話基地局の設置工事、運用・保守といったモバイルエンジニアリングサービスを主力とするインフラテック企業 1。スマートメーター設置サービスなど、IoTインフラ領域にも事業を拡大している 4。
- 投資の論点: 同社はNTTグループを主要な得意先としており、近年のM&Aを通じてNTTグループとの取引拡大を明確に打ち出している 1。銅線廃止の主要な代替手段である「モバイル通信」のインフラ整備は、同社の事業領域そのものである。特に、5G/6Gへの移行が進む中で、基地局の新設・増強需要は継続的に発生する。銅線廃止という明確な期限が設定されたことで、これまで以上に計画的かつ大規模なモバイルインフラ投資が見込まれ、同社は直接的な恩恵を受ける最右翼のグロース銘柄と言える。
JTOWER (4485.T) – シェアリングで5G時代を加速
- 事業内容: 屋内外の通信インフラシェアリング事業を展開 6。商業施設やオフィスビル内の携帯アンテナ設備や、屋外の基地局タワーを複数の通信キャリアで共用するサービスを提供している。5Gやローカル5Gにも対応している 9。
- 投資の論点: 銅線廃止の代替となるモバイル通信網の拡充には、膨大な数の基地局設置が必要となる。JTOWERのインフラシェアリングは、通信キャリア各社が個別に設備を設置するよりもコストを抑え、景観にも配慮できるため、今後の基地局整備において主流な手法となる可能性が高い。特に都市部や大型施設でのカバレッジ向上が急がれる中で、同社の屋内インフラシェアリング(IBS)事業は大きな成長機会を持つ。NTTの決定は、5Gインフラ整備を加速させる強力な追い風となり、同社の事業を直接的に後押しする。
ソラコム (147A.T) & ミーク (332A.T) – IoT化の波に乗るプラットフォーマー
- 事業内容:
- ソラコム: IoTデバイス向けの通信プラットフォーム「SORACOM」をグローバルに提供する 10。KDDIグループの一員であり、IoTに必要なデバイス、通信、クラウド連携をワンストップで提供する 12。
- ミーク: IoT/DXプラットフォーム「MEEQ」と、MVNO事業者を支援するMVNE事業を展開 14。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクの国内3キャリアに対応した通信サービスを提供できる点が強み 16。
- 投資の論点: 銅線廃止は、これまでアナログ回線やISDN回線に接続されていた無数の業務用機器(例:ガス・水道メーター、決済端末、工場のセンサー、監視カメラなど)が、一斉にモバイル通信網へ移行する巨大な需要を生み出す。この「IoT化」の波を捉えるのが、ソラコムやミークのようなIoTプラットフォーマーである。両社は、多種多様なIoTデバイスに最適な通信回線を容易に提供するサービスを展開しており、この移行需要を直接取り込むことができる。特に、毎月の通信料が収益となるリカーリングモデルは、安定した収益成長に繋がるビジネスモデルとして魅力的である 13。
ギックス (9219.T) – データ活用の未来を見据える先駆者
- 事業内容: 企業が保有するデータを活用した戦略コンサルティングや、データ分析プラットフォームの提供を行う「データインフォームド」事業を展開 19。
- 投資の論点: この銘柄は、直接的なインフラ構築の恩恵を受けるわけではないが、その先の未来を見据えた投資対象として興味深い。銅線が光ファイバーや5Gに置き換わることで、日本中のデータ通信量は飛躍的に増大し、質も向上する。これにより、これまで取得・活用が難しかった膨大なデータをビジネスに活かす「データ駆動型経営」が、あらゆる業界で必須となる。ギックスは、まさにそのデータ活用を支援する専門家集団であり、インフラの高度化が進めば進むほど、同社のコンサルティングや分析サービスの需要は中長期的に高まっていくと考えられる。NTTのインフラ変革がもたらす「データの洪水」をビジネスチャンスに変える、間接的ながら大きなポテンシャルを秘めた銘柄である。