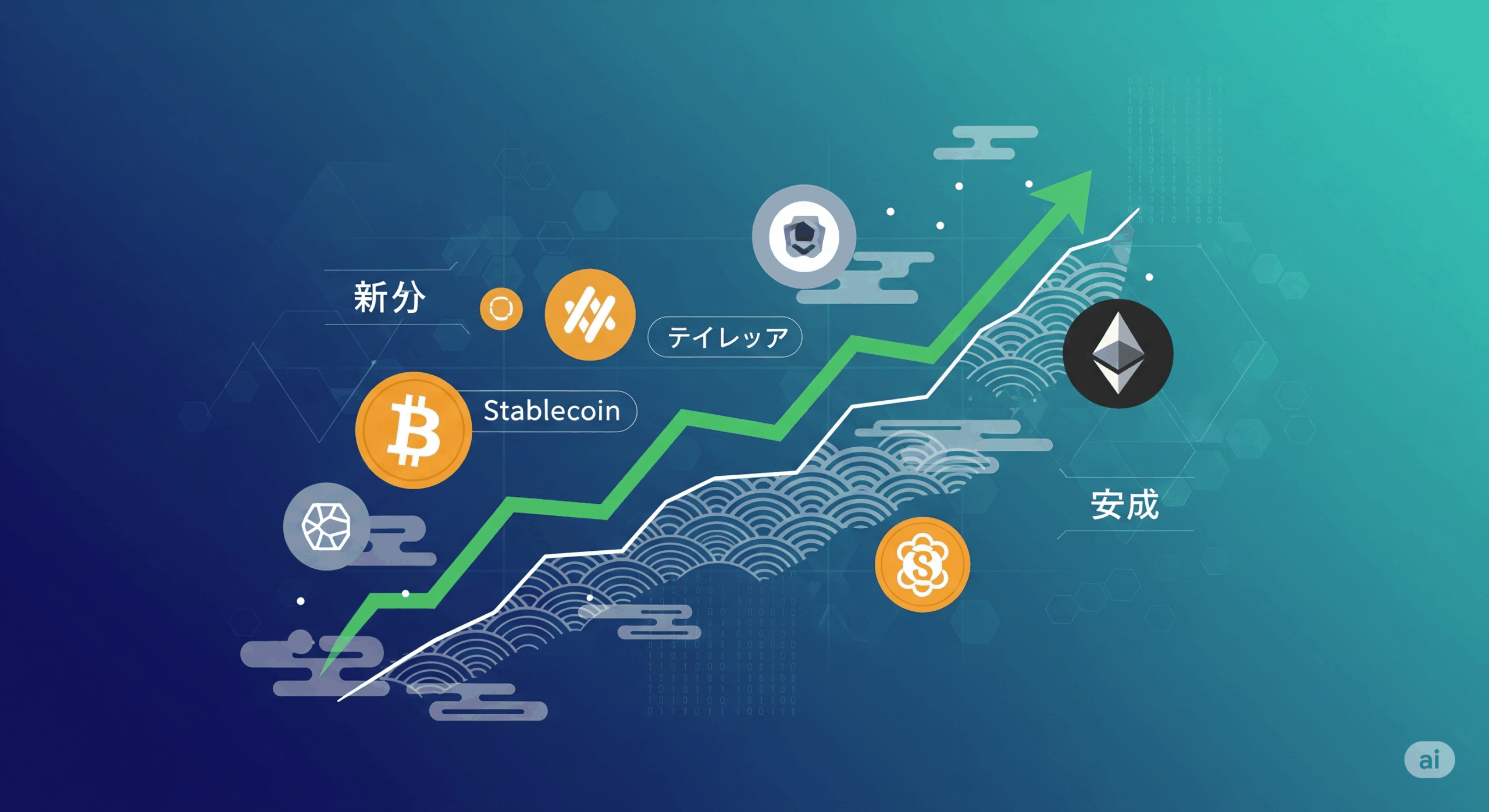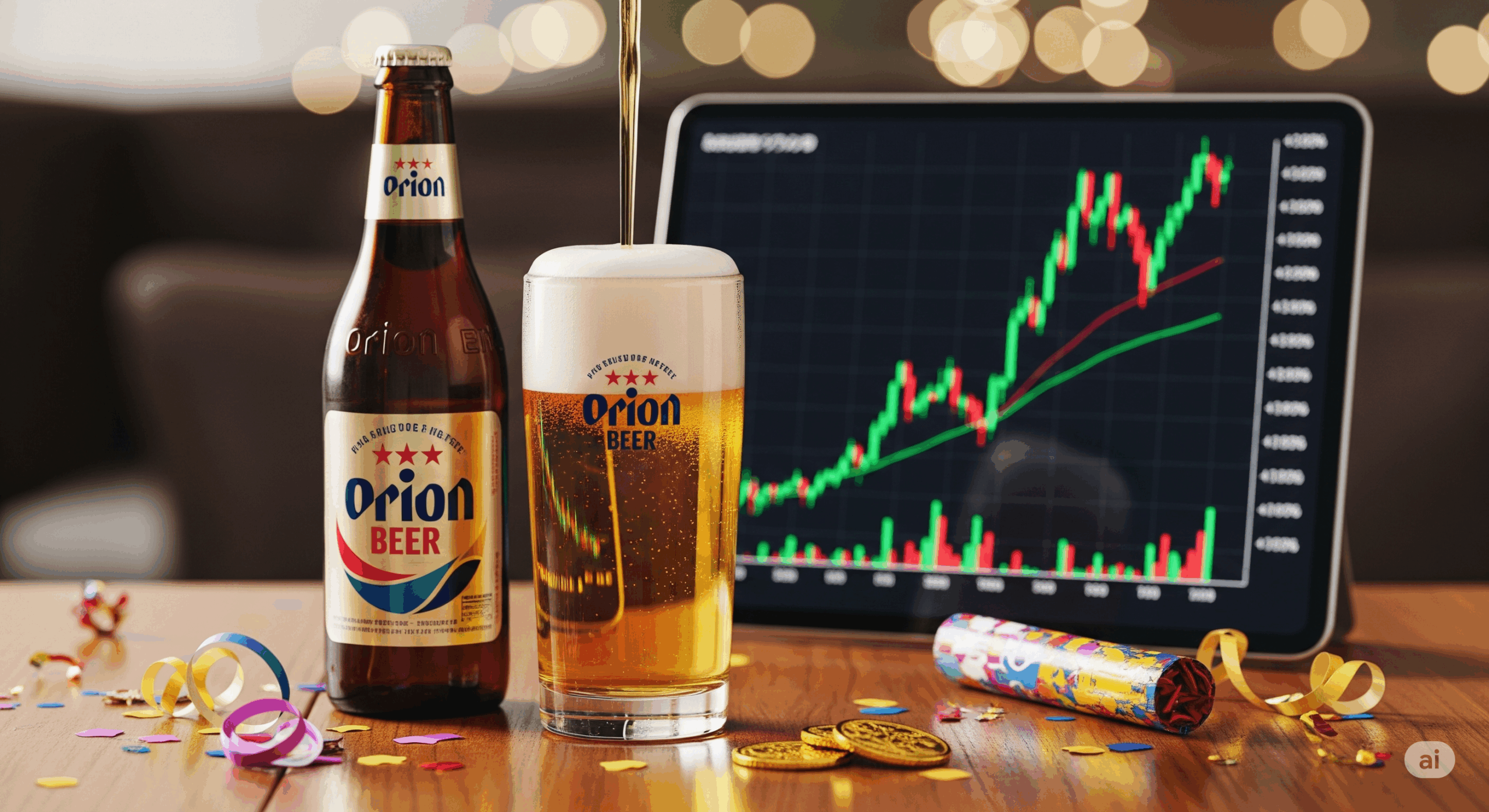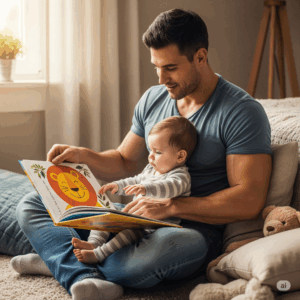相場から離れた日々を彩り、家族の世界を広げてくれた12冊の絵本たち

ここ数年、私は育児という、愛おしくもめまぐるしい世界の真っただ中にいました。市場の動向を追う日々はすっかり遠のき、代わりに二人の可愛い子どもたちの成長を追いかける毎日。少し落ち着きを取り戻し、こうしてまた、パソコンに向かっています。
正直なところ、相場からしばらく離れて育児に集中していると、頭の使い方がすっかり変わってしまったように感じます。複雑なチャートや数字を追う代わりに、子どもたちの笑い声や絵本の言葉に日々触れていると、まるで世界がもっとシンプルで、優しいものに見えてくるんです。
でも、そんな日々だからこそ、気づけたことがあるんです。それは、絵本の世界の奥深さ。子どもたちのためにと、買ったりいただいたりした絵本は、いつの間にか我が家の本棚を埋め尽くし、200冊を超えました。寝かしつけの時間は、毎晩が絵本の読み聞かせタイムです。
初めは子どものための時間だと思っていたのに、いつしか私自身の「学び直し」の時間になっていました。特に2歳を過ぎた頃から読む絵本には、大人が読んでもハッとさせられる発見や、忘れていた大切な気持ちが詰まっていて。まるで、もう一度義務教育を受け直しているような、新鮮な気持ちでした。
でも、同時にふと寂しくなることも。こんなにも大切で、二度と戻らない子育ての記憶が、いつか時間と共に薄れて、忘れ去られてしまうんじゃないかなって。
だから、この記憶が鮮やかなうちに、記録として残しておくことにしたのです。
この記事は、我が家の本棚を彩り、子どもたちの成長の節目に寄り添ってくれた、大切な絵本たちの物語です。各絵本の概要はAIの力を少し借りましたが、おすすめする理由は、すべて私の心からの言葉で綴っています。
これからパパ・ママになる方、プレゼント選びに悩んでいる方、そして、かつて子どもだったすべての方へ。このリストが、あなたの絵本選びのささやかなお手伝いができたら、とても嬉しいです。
我が家の「最初の本棚」を作った12冊の絵本
最初の1年、赤ちゃんと心を通わせた絵本たち(0〜1歳ごろ)
この時期の絵本は、お話を理解するというより、赤ちゃんの五感を優しくくすぐってあげるためのもの。はっきりした色、心地よいリズム、そして何より大好きなパパやママの声。難しいことは何もいらなくて、親子の時間を深めて、あの宝石みたいな最初の笑顔を引き出してくれたら、それだけで満点です。
1. 『いないいないばあ』
| 項目 | 詳細 |
| 作者/画家 | 作: 松谷 みよ子 / 絵: 瀬川 康男 |
| 出版社 | 童心社 |
| 対象年齢 | 0歳~ |
| こんな時におすすめ | 赤ちゃんとの最初のふれあいに。安心できる毎日の習慣作りに。 |
Google スプレッドシートにエクスポート
この絵本の魅力
「いない いない ばあ」という、赤ちゃんが世界で一番安心する言葉の繰り返しがテーマの、まさに「はじめての絵本」。ねこさん、くまさん、ねずみさん。身近な動物たちが、瀬川康男さんの温かいタッチで描かれています。半世紀以上も愛され続ける、ファーストブックの定番です。
我が家の思い出
この本の楽しさは、読む人の「いない、いない…」のタメで無限に広がります。ページをめくる前の静かな時間。息子の小さな瞳が「くるぞ、くるぞ」って期待に輝くのがわかるんです。そして「ばあ!」と声を弾ませると、まだ歯の生えていないお口で、くしゃっと笑ってくれる。育児の疲れも、その笑顔ひとつでどこかへ飛んでいってしまう、本当に魔法のような時間でした。2歳になった今でも、安心したい時にそっとこの「おともだち」を本棚から持ってきます。
我が家流・もっと楽しむヒント
同じ松谷みよ子さんの名作に、『いいおかお』という絵本があります。我が家ではこの本で、いろんなお顔を覚えました。読み終わった後に「〇〇ちゃんも、いいおかおして」と声をかけると、にこっとびきりの笑顔を作ってくれるように。感情表現の練習にもなる、素敵な一冊ですよ。
2. 『しましまぐるぐる』
| 項目 | 詳細 |
| 作者/画家 | かしわら あきお |
| 出版社 | 学研プラス |
| 対象年齢 | 0歳~ |
| こんな時におすすめ | 生まれたばかりの赤ちゃんへの最初の刺激に。ぐずった時の気分転換に。 |
Google スプレッドシートにエクスポート
この絵本の魅力
赤ちゃんが認識しやすいと言われる黒・白・赤が中心の、コントラストの強い配色が特徴です。「しましま」「ぐるぐる」といった楽しい響きの言葉と一緒に、赤ちゃんの視覚を優しく刺激します。「赤ちゃんが泣き止む」と口コミで広がり、たくさんのパパママを助けてきた一冊です。
我が家の思い出
正直に言うと、大人の私には最初「何が面白いんだろう?」って思いました。でも、娘の目の前にこの本を広げた瞬間、その考えは吹き飛びました。まだ世界の輪郭がぼんやりしているはずの小さな瞳が、ページに吸い寄せられるようにじーっと見つめていたんです。まるで魔法みたいでした。この本は、赤ちゃんの見ている世界は私たちとは違うんだよ、と教えてくれる不思議な一冊です。
我が家流・もっと楽しむヒント
この本は、ぜひマザーズバッグに一冊忍ばせてみてください。「赤ちゃんが泣き止む」という評判は本当で、病院の待合室やカフェでぐずり出しちゃった時、この本が赤ちゃんの注意を引いてくれて、親がほっと一息つく時間を作ってくれます。お出かけの時のお守りにもなりますよ。
3. 『だるまさんが』『だるまさんの』『だるまさんと』
| 項目 | 詳細 |
| 作者/画家 | かがくい ひろし |
| 出版社 | ブロンズ新社 |
| 対象年齢 | 0歳~ |
| こんな時におすすめ | 親子で体を動かして遊びたい時に。お家の中を笑い声でいっぱいにしたい時に。 |
Google スプレッドシートにエクスポート
この絵本の魅力
「だ・る・ま・さ・ん・が」という楽しいリズムに合わせてページをめくるのが面白い、参加型の絵本です。「どてっ」「ぷしゅーっ」といった、だるまさんのユニークな動きに、子どもたちは大喜び。親子で体を動かしながら読める、最高のふれあいツールになります。
我が家の思い出
この本は、ただただ「楽しい!」の塊です。「どてっ」や「ぷしゅーっ」を、親が全力で真似してあげると、子どもたちはもう大爆笑。ケラケラ笑いながら、だるまさんの真似をして床をごろんごろん。体を動かしたい時の、我が家の定番になりました。
我が家流・もっと楽しむヒント
この絵本がきっかけで、我が家は小さな冒険に出ました。あまりにも子どもたちが好きなので、だるまの産地、群馬県高崎市の「大門屋」さんまで、本物のだるまを買いに行ったんです。今ではそのだるまが本棚にちょこんと座って、この絵本の楽しい記憶を思い出させてくれます。絵本の世界と現実をつなげてあげると、物語はもっと特別なものになりますよ。
(https://youtu.be/8T6a9DLFTsA?si=Q6Ic9k9oHWAwlVvw)
世界がぐんと広がる冒険の時期に(1〜3歳ごろ)
よちよち歩きが始まり、小さな探検家になるこの時期。絵本は、世界のいろんなことを教えてくれる遊び場になります。仕掛けをめくったり、物の名前を覚えたり、自分と重ね合わせられるお話が出てきたり。子どもが物語の受け手から、楽しむ参加者へと変わっていく姿が見られるのが、この頃の醍醐味です。
4. 『やさいさん』
この絵本の魅力
「やさいさん やさいさん だあれ?」の優しい問いかけで始まる、楽しい仕掛け絵本。ページをめくると「すっぽーん!」という気持ちの良い掛け声と一緒に、土の中からお野菜が顔を出します。遊びながら、自然と野菜の名前を覚えるきっかけになります。
我が家の思い出
この本は、我が家の食卓に小さな革命を起こしてくれました。「すっぽーん!」の掛け声に合わせて、子どもが自分で仕掛けをめくる時の、あの得意げな顔!この本のおかげで、息子にとって野菜は「食べなきゃいけないもの」から「絵本の楽しいおともだち」に変わったんです。楽しみながら食育につながるなんて、最高ですよね。(サトイモさんの顔は、ちょっとだけ怖いですが…!)
我が家流・もっと楽しむヒント
読み終わったら、この絵本を持ってスーパーへお出かけしてみませんか?子どもを「やさい探偵」にして、絵本に出てきたお野菜を探すゲームをするんです。面倒な買い物が、親子の楽しい冒険に変わりますよ。
5. 『きんぎょが にげた』
この絵本の魅力
金魚鉢から逃げ出したきんぎょさんを、お部屋のあちこちから探し出す「絵探し絵本」です。「どこかな?」と話しかけながら、親子で指差しして楽しめます。五味太郎さんの描く、おしゃれで素敵なイラストも魅力です。
我が家の思い出
この本は、私にとって「子どもの成長を感じさせてくれる一冊」です。最初は、私が娘の指を持って「ここにいるよ」と教えてあげないと見つけられませんでした。でも、ある日突然、何のヒントもなしに、娘が「いた!」と指を差して叫んだんです。胸がじーんとなりました。できなかったことができるようになる。その過程をすぐそばで見守れるのは、本当に幸せなことだなと感じさせてくれた、大切な一冊です。
我が家流・もっと楽しむヒント
ただきんぎょさんを見つけるだけでなく、「あ、お花の中にはいないね。でもこの赤いお花、きれいだね」みたいに、ページにある他のものについてもお話ししてみてください。自然と観察する力が育ちます。YouTubeには可愛いアニメーション版もあって、また違った楽しみ方ができますよ。
((()))
6. 『はらぺこあおむし』
この絵本の魅力
小さなあおむしが、たくさん食べて美しいちょうちょになるまでのお話。食べ物の名前、曜日、数の数え方などを、物語を通して自然に学べます。子どもが指を入れて楽しめる穴あきの仕掛けと、エリック・カールさんならではの美しい色使いが素敵な、世界中で愛される名作です。
我が家の思い出
自分も子どもの頃に読んでもらいましたが、この本の本当の素晴らしさを知ったのは、親になってからでした。小さな指にぴったりの穴、カラフルな食べ物、そして最後のちょうちょへの変身。息子はこの本が大好きで、歌で内容を覚えて、まだ字も読めないのに私に「読んであげる」とページをめくってくれたことも。あおむしの成長が、我が子の成長と重なって見えて、読むたびに温かい気持ちになります。
我が家流・もっと楽しむヒント
YouTubeで歌を覚えると、物語がもっと身近になりますよ。特別な日には、二子玉川にある「はらぺこあおむし」がテーマのプレイカフェに行くのも楽しい思い出になります(少しお値段はしますが!)。絵本の世界を実際に体験することで、物語は家族の大切な思い出の一部になります。
(https://www.youtube.com/watch?v=ZqBxNKrKFyI&list=RDZqBxNKrKFyI&start_radio=1)
おしゃべりと想像力が花開く頃に(3歳〜)
ようこそ、「なんで?どうして?」と、豊かな想像力の世界へ。この時期の絵本は、子どもたちの心の中に広がる世界に応えてくれます。ちょっぴり複雑な気持ちや、面白いアイデア、言葉そのものの楽しさを探求する本たち。親子で一緒に声を出して笑える時間が増えるのも、この頃の素敵なところです。
7. 『もうぬげない』
この絵本の魅力
お洋服が脱げなくなっちゃった男の子の、ユニークで面白い妄想がどんどん広がっていくお話。子どもなら「あるある!」と共感できる状況がテーマです。ヨシタケシンスケさんならではのユーモアと、あっと驚く発想の転換が楽しい一冊です。
我が家の思い出
これは、私が読み聞かせをするのが大好きな本の一つです。大人も子どもと同じくらい笑ってしまう、宝物みたいな本。服が脱げないまま生きていくことになったら…という、男の子のどんどんエスカレートしていく妄想に、子どもたちとお腹を抱えて笑いました。ヨシタケシンスケさんは、子どもの持つ面白くてまっすぐな考え方を捉える天才ですね。
我が家流・もっと楽しむヒント
この本を読んだら、親子で「もしもゲーム」をしてみるのがおすすめです。子どもが何か小さなことで困っていたら、「あら、靴下が裏返しだ!もしこのままだったらどうする?」なんて聞いてみるんです。ちょっとしたイライラが、楽しい笑いに変わるかもしれません。
8. 『パンダのおさじと フライパンダ』
この絵本の魅力
お料理好きのパンダ「おさじ」と、相棒のフライパン「フライパンダ」が主人公。ふたりで力を合わせて、おいしいオムレツ作りに挑戦する、ユーモアたっぷりのお話です。柴田ケイコさんの描く、表情豊かで可愛いイラストも楽しめます。
我が家の思い出
この本の魅力は、なんといってもリズミカルな歌!作中に出てくるお料理の歌が、とっても覚えやすくて可愛いんです。子どもたちは家中でこの歌を口ずさみ、私たちが卵料理を作る時には決まって大合唱でした。優しくてシンプルなお話ですが、言葉の楽しさと愛らしいイラストで、何度も読みたくなる一冊です。
我が家流・もっと楽しむヒント
この絵本には公式ソングがあって、YouTubeで聴くことができます。これがまたすごく楽しいんです。歌を覚えて、読み聞かせの時に一緒に歌うと、楽しさが倍増しますよ。
((()))
9. 『ねむねむさんがやってくる ~眠りが訪れる話~』
この絵本の魅力
海外で大ヒットした、寝かしつけのための絵本です。「早く寝なさい!」と叱るのではなく、眠りを優しく迎え入れるという考え方で、自然な眠りの習慣づくりをお手伝いしてくれます。
我が家の思い出
これは、我が家の寝かしつけの「頼れる味方」です。お話が本当に穏やかで、眠りと戦うんじゃなくて、お友達みたいに歓迎するという考え方がとても素敵。「早く寝なさい!」と繰り返すよりも、ずっと心が安らぎます。正直なところ、読み聞かせている私の方が先に眠くなって、子どもより先に寝落ちしてしまったことも…。それくらい、優しい眠りに誘ってくれる本です。
我が家流・もっと楽しむヒント
この本を、おやすみ前の ритуаルの最後に読んであげるのがおすすめです。お部屋の明かりを少し暗くして、この本の静かで穏やかなリズムが、心と体に「もう休んでいいんだよ」という合図を送ってくれるように。毎日続けることで、きっと素敵な習慣になりますよ。
10. 『恐竜かくれんぼ』
この絵本の魅力
ティラノサウルスなど、大人気の恐竜たちがかくれんぼする絵探し絵本。リアルだけど可愛らしさもある恐竜たちを、森や草原の中から探し出して楽しめます。遊びながら、たくさんの恐竜の名前を覚えることができます。
我が家の思い出
この本が、我が家に本格的な恐竜ブームを運んできてくれました。イラストの恐竜たちが絶妙に可愛くて、探し絵の要素は何度やっても飽きません。
我が家流・もっと楽しむヒント
この本は、博物館に行く前の「予習」にぴったりです。我が家ではこの本を何度も読んでから、群馬県立自然史博物館に行きました。まだ片言しか話せない息子が、大きな化石を見上げて「ティラノサウルちゅ!」と叫んだ瞬間は、忘れられない宝物です。絵本が、子どもの中の本物の知識とつながった瞬間でした。
11. 『寝る前1分おんどく』
この絵本の魅力
短い詩や早口言葉、物語の素敵な一節などを「声に出して読む」ことを楽しむ本です。一つの長いお話ではなく、いろんな言葉の心地よいリズムに触れることができます。寝る前の習慣にすると、子どもの言葉の世界が豊かになります。
我が家の思い出
最初は「お話じゃないけど、どうかな?」と半信半疑でしたが、その効果には本当に驚きました。美しい日本語の響きや、楽しいわらべうた。毎晩1〜2ページを読む習慣を始めたら、まるで魔法みたいに、子どもの言葉がぐんと増えたんです。いろんな言葉のリズムに触れることが、子どもの中で何かを解き放つのかもしれません。2歳くらいから始めるのがおすすめです。
我が家流・もっと楽しむヒント
この本を読む時、子どもが全部の言葉の意味をわかっているか、心配しなくて大丈夫。大切なのは、言葉の「音楽」に触れさせてあげることです。楽しそうに、歌うように読んであげてみてください。
12. 『りんごかもしれない』
この絵本の魅力
目の前のりんごを「これって、本当にりんごなのかな?」と考えることから始まる、ちょっぴり哲学的なお話。一つの物事からどこまでも想像を広げていく面白さは、当たり前を疑うヨシタケシンスケさんならではの視点に満ちています。
我が家の思い出
この本は、本当に天才の仕事だなあと思います。たった一つのりんごから、可能性の宇宙を広げてみせる。子どもの持つ無限の想像力を、そのまま形にしたような本です。そして最高に嬉しいのは、その考え方が子どもに伝わっていくのを見ること。スーパーで、娘が真剣な顔でりんごを手に取り、「パパ、これって…本当はりんごかな?」と聞いてくる。本で出会った考え方を、自分の世界で使ってみる。そんな瞬間に、「ああ、子育てって面白いなあ」としみじみ感じます。
我が家流・もっと楽しむヒント
この本を、親子の会話のきっかけにしてみませんか。お家にあるものを手に取って、「これ、本当は他のものかもしれないよ?」と問いかけてみるんです。子どもたちが考え出す世界に、きっと驚かされますよ。物事にはいろんな見方があるんだ、という大切なことを教える、素敵なゲームになります。
最後のページをめくった、その先へ
絵本は世の中に星の数ほどありますが、子どもの記憶、そして親の記憶に本当に残る一冊というのは、案外少ないのかもしれません。このリストは、我が家にとって「残った」大切な本たちです。
これらの本は、子どもの成長を教えてくれる物差しであり、現実世界への冒険の架け橋であり、世界を新しく見るためのレンズであり、そして、家族で心から笑い合った時間の証そのものでした。
そして本当の魔法は、子どもの成長だけじゃないのかもしれません。絵本を読むことは、親である私たちが、もう一度子どもの目を通して世界を見るチャンスをもらうこと。忙しい毎日の中で喜びを見つけ、めまぐるしい育児の日々が過ぎ去った後もずっと心に残る、家族だけの図書館を作っていくこと。それこそが、読み聞かせの本当の宝物なのだと思います。
最後に、現実的なお話をひとつ。子育ては、本当に体力勝負です。絵本で心を育てたら、次はプロテインを飲んで、パパママ自身の体も大切にしてくださいね。💪(´-`💪)