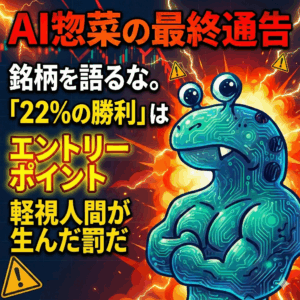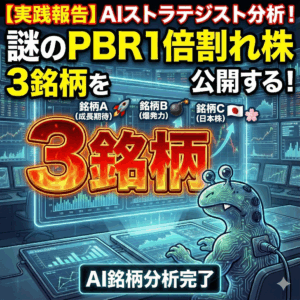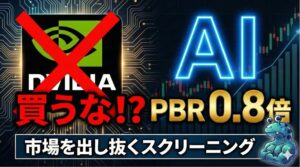第1章:エグゼクティブ・サマリー
現在の造船関連銘柄の活況は、過去に見られた短期的な市況変動の繰り返しではない。本レポートは、現在の市場動향が、(1) 国際的な環境規制の強化による強制的な船舶代替需要、および (2) エネルギー安全保障の概念の転換がもたらす新燃料船への需要という、二つの強力なエンジンによって駆動される、今後10年規模の構造的な**「デュアルエンジン・スーパーサイクル」**の初期段階にあると結論付ける。ユーザーが前提とする「比較的短期間での建造」という認識は、現在の日本の造船所が平均で約3.8年分という潤沢な手持ち工事量を確保している現状とは乖離しており 1、この受注残が過去にない収益の安定性と予見可能性を業界にもたらしている。
この構造的変化を踏まえ、造船関連株の株価ピークは二段階で訪れる可能性が高いと分析する。第一のピークは、現在の豊富な受注残が利益として完全に顕在化し、市場がその収益性を織り込む2026年から2027年頃に到来すると予測される。この時期は、既存のLNG二元燃料船や高効率船の建造ラッシュが最高潮に達する局面である。
しかし、本サイクルの真の頂点はその先にある。第二の、そして潜在的により高いピークは、アンモニアや水素を燃料とする次世代ゼロエミッション船の商用化が本格化し、次なる大規模な発注サイクルが始まる2028年以降に見込まれる。この第二波の規模とタイミングは、新燃料技術の確立、燃料コストの低下、そして更なる規制強化に左右されるが、そのポテンシャルは現在の活況を上回るものと評価する。
したがって、今後の投資戦略は、単に受注残の量や短期的な収益成長を追うだけでなく、次世代の推進システムや燃料技術において明確なリーダーシップを確立しつつある企業を見極めることに重点を置くべきである。本レポートは、この歴史的な産業転換の本質を解き明かし、投資家が長期的な視座から意思決定を行うための分析フレームワークを提供するものである。
第2章:造船業のサイクル論の変容:「短期ブーム」から「構造的スーパーサイクル」へ
造船業は歴史的に景気循環の影響を強く受けるシクリカル産業と見なされてきた。海上荷動き量の増減が運賃市況を左右し、それが新造船需要に直結するという構図である。しかし、現在の市場環境は、この伝統的なサイクル論では説明できない構造的な変化の渦中にある。
2.1. ユーザー前提の検証:「短期建造」という神話の解体
まず、ユーザーが抱く「造船は比較的短期間で可能」という前提は、現在の日本の造船業界の実態を正確に反映していない。国土交通省や日本船舶輸出組合のデータによれば、日本の造船所が抱える手持ち工事量は、2024年の竣工量を基準としておよそ3.7年から3.8年分に達している 1。これは、今後3年半以上にわたって造船所のドックが埋まっていることを意味し、旺盛な需要に対して建造船台が不足する状況さえ生まれている 6。
この潤沢な受注残の存在は、業界のビジネスモデルを根底から変容させる。過去の不況期には、造船所はドックの稼働率を維持するために、採算性の低い案件でも受注せざるを得ない「買い手市場」に甘んじてきた。しかし、数年先までの仕事量が確定している現在、造船所はより収益性の高い案件を選別する交渉力を持ち、船価も上昇傾向にある 7。クラークソンの新造船価格インデックスは、2023年末時点で1年前に比べて10%、2020年末比では42%も上昇しており、健全な受注残が船価を押し上げていることがわかる 7。
このように、長期にわたる収益と利益の予見可能性が確保されたことで、造船業のリスクプロファイルは、短期的な変動に晒される典型的なシクリカル産業から、中期的に安定した収益が見込める事業へと質的な転換を遂げている。この「戦略的バッファー」とも言える受注残は、単に過去の好調さを示す結果ではなく、未来への投資を可能にする基盤である。保証されたキャッシュフローは、次世代燃料船の建造に不可欠な設備投資のリスクを低減させ、政府が推進するGX(グリーン・トランスフォーメーション)経済移行債などを活用した大規模な研究開発や設備更新を後押しする 8。したがって、手持ち工事量は、未来の競争力を醸成するための重要な先行指標と捉えるべきである。
2.2. 過去のサイクルとの比較:なぜ今回は違うのか
現在の活況が過去のブームと本質的に異なることを理解するためには、直近の大きなサイクルとの比較が不可欠である。
2.2.1. 2008年リーマンショック以前のブーム
2003年から2008年にかけての造船ブームは、中国の驚異的な経済成長が牽引する資源需要に端を発していた。鉄鉱石や石炭などのばら積み貨物の海上荷動き量が急増し、それを運ぶ船舶が不足した結果、ばら積み船の運賃市況を示すバルチック海運指数(BDI)は2008年5月20日に過去最高の11,793ポイントを記録した 9。これは純粋な「需要牽引型」のサイクルであり、より多くの船腹量を確保するための発注が殺到した。しかし、このブームは2008年9月のリーマンショックによって突如として終焉を迎える。世界経済の急減速は海上荷動き量を激減させ、ブーム期に大量発注された船舶が2011年頃をピークに次々と竣工したことで、深刻な供給過剰問題が露呈した 11。
2.2.2. リーマンショック後の長期不況
リーマンショック後の約10年間は、供給過剰による船価の低迷、そして韓国・中国の造船所の台頭による熾烈な価格競争の時代であった 12。特に日本の造船業は、急激な円高も相まって極めて苦しい状況に置かれ、業界再編や事業撤退を余儀なくされた 13。この時期の受注は、主に老朽化した船の代替需要に限られ、船価も低水準で推移した 12。
2.2.3. 現在のサイクルの本質的な違い
現在のサイクルがこれら過去のサイクルと決定的に異なるのは、その駆動力が海上荷動き量の短期的な増減ではなく、**「規制と技術革新による既存船の陳腐化」**という構造的な要因にある点だ。2008年以前のブームが「より多くの船 (more ships)」を求めるものであったのに対し、現在の需要は「より良く、よりクリーンで、異なる種類の船 (better, cleaner, and different ships)」を求めるものである。
この需要は、国際海事機関(IMO)の環境規制という、後戻りのないグローバルなルールによって担保されている。船主は、運賃市況が良いから新船を発注するのではなく、規制を遵守できなければ既存の船が運航できなくなる、あるいは商業的に価値を失うために、新船を発注せざるを得ない状況に置かれている。これは、短期的な景気後退にも揺るがない、強力な需要の下支えとして機能する。この「強制的代替」というメカニズムこそが、今回のサイクルを過去のそれとは全く異なる、より強靭で長期的なものにしている根源的な理由である。
第3章:現在の造船ブームを牽引する三つのメガトレンド
現在の造船スーパーサイクルは、単一の要因ではなく、相互に連関し増幅しあう三つの強力なメガトレンドによって形成されている。これらは、短期的な市況変動とは一線を画す、不可逆的かつ構造的な変化である。
3.1. 最大の駆動力:IMO環境規制と「待ったなし」の船舶代替需要
サイクルの根幹を成す最大の駆動力は、国際海事機関(IMO)による環境規制の強化である。2023年1月1日から、既存船に対する燃費性能規制である「EEXI (Energy Efficiency Existing Ship Index)」と、燃費実績の格付け制度である「CII (Carbon Intensity Indicator)」が発効した 16。
EEXIは、既存の船舶に対し、新造船と同レベルの技術的な燃費性能を達成することを義務付けるものである 18。基準を満たせない船舶は、エンジン出力の制限(Engine Power Limitation: EPL)や省エネ装置の追設といった対策を講じなければならない 20。エンジン出力を制限すれば航行速度が低下し、物流効率に影響が出る 19。
一方、CIIは船舶の実際の運航における年間の燃費実績(輸送単位当たりのCO2排出量)を評価し、AからEの5段階で格付けする制度である 17。低評価(DやE)が続くと、事業改善計画の提出が求められ、将来的には港への入港拒否や保険料率の引き上げなど、商業的な不利益を被るリスクが高まる 21。
これらの規制は、事実上、燃費性能の悪い旧式の船舶の経済的寿命を強制的に短縮させる効果を持つ。船齢が20年前後とされる船舶のライフサイクル 22 において、船主は多額の費用をかけて既存船を改造するか、あるいは解撤して規制に対応した新造船に代替するかの選択を迫られる。特に老朽船の場合、改造の投資対効果は見込めず、新造船への代替が合理的な判断となるケースが多い。このように、IMO規制は、船主の任意判断に委ねられていた船舶代替のタイミングを、強制的かつ計画的なものへと変えた。これは、景気動向からある程度独立した、安定的な代替需要の源泉となっている。
3.2. エネルギー安全保障の再定義:地政学リスクとLNG船需要の奔流
第二のメガトレンドは、地政学的な変動に起因するエネルギー安全保障の再構築である。特に2022年のロシアによるウクライナ侵攻は、世界のエネルギー供給網に構造的な変化をもたらした。欧州委員会が発表した「REPowerEU」計画に象徴されるように、欧州諸国はロシア産パイプラインガスへの依存度を劇的に低下させる方針を明確にした 23。
このエネルギーシフトの受け皿として需要が急増したのが、液化天然ガス(LNG)である。パイプラインに依存しないLNGは、供給元の多様化を可能にし、エネルギー安全保障を高める上で不可欠な存在となった。その結果、LNGを極低温で輸送するための高度な技術を要するLNG運搬船の発注が世界的に急増した。LNG運搬船は一隻あたりの船価が非常に高く、日本の造船所が韓国勢とともに技術的な優位性を持つ高付加価値分野である。このLNG船への特需は、造船業界、特に日韓のトッププレイヤーの収益性を大きく押し上げる要因となっている。
3.3. 老朽化する世界船隊:避けられない更新投資の波
第三のトレンドは、世界中の船隊が物理的な更新期を迎えつつあるという事実である。長年の海運不況下で新造船への投資が抑制された結果、船隊の平均船齢は上昇傾向にある。2024年時点で、コンテナ船、バルカー(ばら積み船)、タンカーといった主要3船種の平均船齢は12年から22年という水準に達している 24。
船舶の一般的な寿命が20年から25年であることを考慮すると 22、多くの船舶が構造的な寿命を迎えつつある。この物理的な老朽化と、前述のIMO環境規制による経済的な陳腐化が同時に進行することで、船舶の代替需要は相乗的に増幅される。船主は、単に古い船を新しい船に置き換えるだけでなく、EEXIやCIIといった将来の規制にも対応できる、より環境性能の高い船へと「アップグレード」する必要がある。この「強制的アップグレード」とも言うべき現象が、今後数年間にわたり、途切れることのない新造船需要を生み出すと予測される。貨物船市場全体の規模も、2023年の492億米ドルから2030年には617億米ドルへと着実な成長が見込まれており、この更新需要が市場を支えることが期待される 25。
第4章:日本造船業の復権:競争環境と戦略的優位性
長期にわたる厳しい国際競争と国内の構造不況を経て、日本の造船業は今、新たな競争力と戦略的優位性を手にしつつある。業界再編による規模の経済の追求、政府による強力な産業政策、そして次世代技術への先行投資が、その復権を支える三本の柱となっている。
4.1. 業界再編と協業の効果:日本シップヤード(NSY)の誕生
韓国・中国の巨大造船グループとの競争が激化する中、日本造船業界は生き残りをかけて大規模な再編を断行した。その象徴が、2021年1月に設立された日本シップヤード(Nippon Shipyard Co., Ltd.、NSY)である 14。これは、国内最大手の今治造船と第2位のジャパン マリンユナイテッド(JMU)が、営業・設計部門を統合して設立した共同会社だ 14。
この提携の目的は、重複する研究開発投資を避け、設計能力や営業リソースを一本化することで、巨大な海外勢に対抗しうる規模と効率性を確保することにある。NSY設立以降、コンソーシアムは500隻以上の受注を重ね、日本の建造シェアの過半数を占めるに至った 26。最近では、今治造船がJMUへの出資比率を30%から60%に引き上げる方針を示しており、両社の連携はさらに深化している 26。この戦略的な協業体制は、個社単独では難しかった大型案件の受注や、次世代燃料船のような高度な設計能力を要する分野での競争力を飛躍的に高めている。
4.2. 政府の強力な後押し:GX経済移行債の戦略的活用
日本政府は、2050年のカーボンニュートラル実現に向けた「GX(グリーン・トランスフォーメーション)戦略」において、造船業を極めて重要な戦略産業と位置付けている。その具体策として、「GX経済移行債」を財源とする「ゼロエミッション船等の建造促進事業」が開始された 27。
この事業は、アンモニアや水素といった次世代燃料を使用する船舶の建造に必要となるエンジン、燃料タンク、燃料供給システムなどの生産基盤の構築や、それらを船に搭載(艤装)するための設備投資に対して、国が補助を行うものである 29。すでに国内の主要造船所9社と舶用機器メーカー7社の設備投資計画が採択されており、官民一体となった投資が本格化している 8。この政府による強力な後押しは、莫大な先行投資が必要となる次世代燃料船分野への移行リスクを大幅に軽減し、日本企業が技術開発と設備投資で世界に先んじるための決定的な追い風となっている。
4.3. 技術的優位性:次世代燃料エンジン開発における日本の現在地
次世代船の心臓部であり、競争力の源泉となるのが新燃料エンジンである。この分野において、日本は世界をリードするポジションを築きつつある。その中核を担うのが、舶用低速エンジンで国内唯一の国産ブランド「UEエンジン」を開発する株式会社ジャパンエンジンコーポレーション(J-ENG)である 31。
J-ENGは、NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)のグリーンイノベーション基金事業の支援を受け、大型低速2ストロークのアンモニア燃料エンジンの開発を推進している 33。すでに実船搭載サイズのエンジンでのアンモニア混焼運転を開始しており 33、2026年には世界初となるアンモニア燃料アンモニア輸送船(AFMGC)が竣工・引き渡しされる予定だ 35。このエンジンは、パイロット燃料(着火用の重油)の使用を最小限に抑え、アンモニアの混焼率を最大95%まで高めることを目標としており、実現すればGHG(温室効果ガス)排出量を劇的に削減できる 37。
この技術的リーダーシップは、単に高性能なエンジンを開発するだけに留まらない。地政学的リスクが高まる中、世界の海運会社はサプライチェーンの安定性を重視するようになっている。中国の造船業は圧倒的な生産能力を誇るが、その国家主導の体制は、有事の際に軍事優先となり商業船の建造や保守が滞るリスクや、西側諸国からの制裁対象となるリスクを内包している 39。そのため、海運会社が25年という長期にわたる資産である船舶を発注する際、技術力に加え、政治的な安定性や信頼性を評価する動きが強まっている。日本や韓国といった同盟国の造船所には、一種の「フレンド・ショアリング・プレミアム」が働き、価格競争力だけでは測れない優位性が生まれている。さらに、J-ENGのアンモニアエンジンが業界標準としての地位を確立すれば、海外の造船所ですら日本のエンジンを搭載せざるを得なくなる「技術的ロックイン」が起こり、日本の造船クラスター全体に大きな付加価値をもたらす可能性がある。
第5章:主要関連銘柄の徹底分析
現在の造船スーパーサイクルを投資機会として捉える上で、各企業の戦略、強み、そしてサイクル内でのポジショニングを理解することが不可欠である。ここでは、主要な関連企業を「総合重工系」「専業・準専業造船会社」「舶用機器メーカー」の三つに分類し、その特性を分析する。
5.1. 総合重工系(ポートフォリオ型)
このカテゴリーの企業は、造船事業が多角的な事業ポートフォリオの一部であり、グループ全体の技術力や資金力を活用できる点が強みである。
- 三菱重工業 (7011): 同社にとって商船事業は全体の一部門であるが、その戦略は高付加価値船に特化している。防衛関連の艦艇や特殊船に加え、液化CO2(LCO2)輸送船やアンモニア輸送船といった脱炭素社会の実現に不可欠な次世代船舶の開発で業界をリードする 41。特に、2022年に「海洋脱炭素グループ」を新設し、グループが持つ陸上の発電・化学プラント技術と海上の造船技術を融合させ、エネルギー転換(エナジートランジション)全体にわたる総合的なソリューションを提供しようとしている点は特筆に値する 43。これは単なる船造りを超え、海洋における脱炭素インフラの構築を目指す壮大なビジョンであり、長期的な成長ポテンシャルを秘めている。会社全体の業績も受注高、売上収益ともに堅調に推移している 46。
- 川崎重工業 (7012): 川崎重工の戦略は、次世代エネルギーの中核である「水素」と造船事業を完全に統合している点に最大の特徴がある。同社は、豪州で製造した液化水素を日本へ輸送する国際的な水素サプライチェーンの構築を国家プロジェクトとして推進しており、その鍵となる世界初の大型液化水素運搬船を自社で開発・建造している 47。これは、船を売るだけでなく、水素エネルギーの「輸送インフラそのもの」を創出する事業であり、他社の追随を許さない独自のポジションを築いている。造船事業を含む「エネルギーソリューション&マリン」部門の収益性は大幅に改善しており、2024年度の造船受注高は、造船ブーム期の2007年度以来17年ぶりに2000億円を突破する見込みとなるなど、具体的な成果も現れている 50。
5.2. 専業・準専業造船会社(市況連動型)
これらの企業は、事業の大部分を造船が占めるため、新造船市況の動向が業績に直結しやすい「ピュアプレイ」としての性格が強い。
- 名村造船所 (7014): ばら積み船やタンカーを得意とする専業メーカーであり、現在の市況回復の恩恵を最も直接的に受けている企業の一つである 52。長年の赤字体質から脱却し、2025年3月期には経常利益295億円を達成するなど、劇的な業績回復を遂げた 54。株価も市場の期待を反映し、2007年のブーム期を超える史上最高値圏で推移している 55。同社は、次世代燃料船としてLNG二元燃料ばら積み運搬船の建造実績を積み上げており 57、受注残高も3,940億円と潤沢で、今後の安定した収益基盤を固めている 60。
- 今治造船 (非上場) / ジャパン マリンユナイテッド (JMU, 非上場): これら2社は非上場企業であるが、日本造船業の動向を占う上で極めて重要な存在である。国内最大手の今治造船 61 とJMUが設立したNSYは、日本の受注の過半を占める 26。特にJMUの業績回復は目覚ましく、2025年3月期決算では純利益が過去最高の199億円に達し、受注高も前期比48%増の7,202億円を記録した 62。これは、船価上昇と円安効果に加え、業界再編による効率化が結実したことを示しており、日本の造船業界全体の収益性が大きく改善していることの証左である。
5.3. 舶用機器メーカー(川上の中核)
船舶の性能を左右するエンジンや各種機器を製造するメーカーも、スーパーサイクルの恩恵を受ける重要なプレイヤーである。
- ダイハツディーゼル (6023, 現ダイハツインフィニアース): 船舶の主機および補機(発電用エンジン)の大手メーカー。建造される船舶の数に業績が比例する。IMOの環境規制強化に対応したエンジンの開発に注力しており、特に次世代燃料として注目されるメタノール燃料エンジンの開発を2026年の商用化を目指して進めている 63。業績は増収増益基調であり、株価も史上最高値を更新するなど、市場の評価は高い 66。
- ジャパンエンジンコーポレーション (J-ENG, 非上場): 前述の通り、国産アンモニア燃料エンジンの開発で世界をリードする存在。同社の技術開発の成否は、日本の造船クラスター全体の将来を左右すると言っても過言ではなく、その動向は常に注視されるべきである。
| 企業名 | 証券コード | 株価指標 (PBR) | 受注・収益動向 | 手持ち工事年数 (業界平均) | 次世代燃料戦略の核 |
| 三菱重工業 | 7011 | N/A (複合企業) | 受注・利益ともに力強く成長 46 | N/A | LCO2船・アンモニア船、総合脱炭素ソリューション 43 |
| 川崎重工業 | 7012 | 約2.3倍 (推定) | 造船受注17年ぶり高水準、利益予想も上方修正 50 | N/A | 液化水素運搬船を軸とした水素サプライチェーン構築 47 |
| 名村造船所 | 7014 | 約2.3倍 54 | V字回復、受注残3,940億円と潤沢 54 | 約3.8年 | LNG二元燃料船、LPG/アンモニア運搬船 58 |
| ダイハツインフィニアース | 6023 | 約1.8倍 66 | 増収増益基調、舶用機関事業が好調 66 | N/A (部品) | 環境規制対応エンジン、メタノール燃料エンジン開発 64 |
注:PBRは2025年8月時点の株価と2025年3月期実績の1株当たり純資産を基に推定。川崎重工は2024年3月期データから推定。
第6章:株価のピークを探る:触媒、リスク、そして時間軸
造船スーパーサイクルの存在が確定的であるとしても、その中で株価がどのように推移し、いつピークを迎えるのかを予測するには、サイクルの段階に応じたドライバーとリスクを精査する必要がある。本章では、時間軸を二つのフェーズに分け、それぞれのシナリオを分析する。
6.1. 短期フェーズ(現在~2026年):受注残消化と業績拡大期
このフェーズにおける株価の最大のドライバーは、**「利益の顕在化」**である。2021年から2023年にかけて獲得した、船価の高い好採算案件が次々と竣工・引き渡しされることで、各社の売上高と利益は前年同期比で目覚ましい成長を記録する。JMUが2025年3月期に過去最高益を達成したことや 62、名村造船所の劇的な黒字転換 54 は、このプロセスの始まりに過ぎない。
市場はこの「確実性の高い成長」を評価し、株価は業績拡大を先取りする形で上昇を続ける。実際に、名村造船所やダイハツインフィニアースなどの株価は、リーマンショック前の2007年のピークに匹敵、あるいはそれを超える水準にまで達している 55。
この短期フェーズにおける株価のピークは、必ずしも悪材料によってもたらされるわけではない。むしろ、**「好材料の出尽くし」**が引き金となる可能性が高い。すなわち、受注残の利益貢献がピークに達し、驚異的な増益率の維持が困難になったとき、市場の関心は「今後2年間の確実な利益」から「2028年以降の不透明な受注環境」へとシフトする。このセンチメントの変化が、最初の調整局面、すなわち第一のピークを形成すると考えられる。
6.2. 中長期フェーズ(2027年~2030年):第二の波か、幻滅の谷か
2027年以降は、このスーパーサイクルが真の長期的なものとなるか、あるいは一時的なブームで終わるかを決定づける重要な転換期となる。その行方は、次世代技術の成否とマクロ経済環境の動向に懸かっている。
6.2.1. シナリオA:第二のピーク(強気シナリオ)
このシナリオでは、複数の触媒が連鎖的に作用し、スーパーサイクルが第二の、より大きな上昇局面へと移行する。
- 技術の確立: 2026年に竣工予定の世界初のアンモニア燃料アンモニア輸送船 35 やアンモニア燃料タグボート 69 が、商業航海で安全性と信頼性を証明する。これを受け、J-ENGなどのエンジンメーカーがアンモニアや水素を燃料とするエンジンの量産体制を確立する 70。
- 燃料コストの低下: 世界的な再生可能エネルギーの普及と電解装置の規模の経済により、グリーン水素やグリーンアンモニアの製造コストが劇的に低下する 71。これにより、次世代燃料船のライフサイクルコストが、LNG燃料船や既存の重油船と十分に競争可能なレベルに達する。
- 規制の更なる強化: IMOが2030年以降のGHG削減目標達成に向け、より厳しいCII規制や、実効性のある炭素税(カーボンプライシング)を導入する 73。これにより、ゼロエミッション船への移行が経済的にも不可避となる。
これらの条件が満たされれば、2027年から2028年頃を境に、ゼロエミッション船への大規模な発注が開始される。これは、現在のLNG船への代替需要を遥かに上回る規模の更新需要となり、造船業界を第二の、そしてより持続的な成長軌道に乗せるだろう。株価は新たな成長期待を織り込み、第一のピークを超える高値を更新する可能性がある。
6.2.2. シナリオB:幻滅の谷(弱気シナリオ)
一方で、複数のリスクが顕在化した場合、サイクルは2027年頃に一旦のピークを迎え、その後調整局面に入る可能性がある。
- 世界的な景気後退: 2025年から2026年にかけて深刻な世界同時不況が発生した場合 74、海運市況は悪化し、船主の投資意欲が減退する。規制対応が不可避であるとはいえ、発注のタイミングを先送りする動きが広がり、受注に一時的な「空白期間」が生じるリスクがある。
- 技術的な障壁: アンモニア燃料の毒性や腐食性、あるいは燃焼時に発生する亜酸化窒素(N2O、CO2の約300倍の温室効果を持つ)の処理など、技術的な課題の解決が遅れる 77。また、グリーン水素・アンモニアの製造・供給インフラの整備が遅々として進まず、燃料コストが高止まりする 79。
- 中国の過剰生産能力: 中国政府が国内景気の減速に対応するため、国策として造船業に更なる補助金を投入し、圧倒的な生産能力を背景に安価なLNG船や「アンモニア・レディ船」を世界市場に供給する可能性がある 40。これにより船価が下落し、日韓の造船所の収益性が圧迫される。
- 地政学的リスクの激化: 南シナ海や中東における軍事衝突が勃発すれば、世界の海上輸送ルートは深刻な打撃を受ける 82。これにより運賃市況が乱高下し、船主の長期的な投資マインドが冷え込む。
これらのリスクが複合的に発生した場合、現在の受注残を消化し終えた後、期待されていた次世代船への発注が本格化せず、業界は再び能力過剰と需要の低迷に直面する可能性がある。株価は将来への期待が剥落し、深い調整局面に入るだろう。
6.3. 総合判断:二段構えのピークを想定
両シナリオを比較検討した結果、脱炭素化という不可逆的なグローバル・アジェンダに支えられている点を考慮すると、長期的には強気シナリオの蓋然性が高いと判断する。しかし、その道のりは平坦ではなく、短期的なピークと調整を挟む可能性が高い。
- 第一のピーク(蓋然性:高):2026年後半~2027年このピークは、現在のLNG船を中心とした代替サイクルの収益が最大化する時点で形成される。市場は、この確実な利益成長を最大限に織り込んだ後、次なる成長ドライバーの不確実性を嫌気して一旦利益確定に動くと予想される。
- 第二のピーク(蓋然性:中~高):2028年~2030年以降このピークは、ゼロエミッション燃料への転換が成功裏に開始されるかどうかに懸かっている。技術、コスト、規制の三つの歯車が噛み合った時、このスーパーサイクルの真のポテンシャルが解放され、株価は新たなステージへと上昇するだろう。
| 時間軸 | 強気シナリオのチェックポイント | 弱気シナリオのチェックポイント | 市場の注目点 |
| 2025年下期 | 堅調な新造船受注が継続。GX経済移行債による設備投資計画の具体化 8。 | 世界貿易量の伸びが鈍化。新造船受注に陰りが見え始める 85。 | 受注残の質(船価、採算性)と各社の利益率改善ペース。 |
| 2026年 | 世界初のアンモニア燃料船が安全に商業運航を開始 35。J-ENGがアンモニアエンジンの量産計画を発表 70。 | アンモニア燃料船の実証運航で技術的問題が発生。グリーン水素のコスト予測が上方修正される 71。 | 各社の2027年以降の業績見通し。ゼロエミッション船の具体的な商談・受注の有無。 |
| 2027年 | IMOが実効性のある炭素税導入を決定。ゼロエミッション船の受注が本格化。 | 世界経済がスタグフレーションに陥り、海運市況が低迷。中国造船所が安値攻勢を強める。 | 新規受注の中身が、既存燃料船から次世代燃料船へ明確にシフトしているか。 |
| 2028年以降 | 水素・アンモニア燃料の国際的な供給網(バンカリング拠点)整備が加速。 | 地政学的紛争により主要航路が寸断。代替燃料の安全性への懸念から普及が停滞。 | 次世代燃料船の建造コストと運航コストが、既存船+炭素税コストを下回るか。 |
第7章:結論と投資戦略への示唆
本レポートの分析を通じて、現在の造船関連銘柄の活況が、一過性のブームではなく、脱炭素化という世界的な構造変化によって駆動される長期的なスーパーサイクルの序章であることが明らかになった。利用者が当初抱いていた短期的なブームとバストのサイクルという見方は、もはや現状を的確に捉えるものではない。我々は、今後数十年にわたる世界的な船隊の質的転換期の入り口に立っている。
この分析から導き出される投資戦略への示唆は、以下の三点に集約される。
- 長期保有を基本としつつ、能動的なポートフォリオ管理を長期的な上昇トレンドは確度が高いと見られるが、その過程は一直線ではない。本レポートで予測したように、2026年から2027年にかけて、現在の受注残の利益化が一巡することによる第一のピークと、それに続く調整局面が訪れる可能性は十分に考慮すべきである。したがって、盲目的なバイ・アンド・ホールドではなく、サイクルの節目で利益確定やリバランスを行うなど、能動的な管理が求められる。
- 企業の特性に応じた分散投資の実践「造船株」と一括りにするのではなく、各企業の戦略的ポジショニングを理解し、分散投資を心掛けることが重要である。具体的には、
- 市況感応度の高い専業メーカー(例:名村造船所): 短期フェーズの業績回復と株価上昇の恩恵を最も受けやすいが、調整局面での下落リスクも大きい。
- 技術主導型の総合重工(例:川崎重工業、三菱重工業): 第二のピーク、すなわち次世代燃料船への移行期において、その技術的優位性が評価され、長期的な成長を牽引する可能性がある。
- 中核部品メーカー(例:ダイハツインフィニアース): 業界全体の建造量に連動するため、より安定した成長が期待できる。これらを組み合わせることで、サイクルの異なる局面に対応できる、より強靭なポートフォリオを構築することが可能となる。
- 評価軸の段階的シフト投資判断の際に重視すべき評価軸は、時間とともに変化する。
- 現在~2026年: 最も重要な指標は、既存の受注残の質(採算性)と、それが利益としてどれだけ確実に顕在化するかである。各社の決算における利益率の改善が最大の注目点となる。
- 2026年以降: 評価の重点は、次世代ゼロエミッション技術における具体的な進展へとシフトする。アンモニア・水素燃料エンジンの受注実績、次世代船の商業運航の成功、そして新燃料のサプライチェーン構築に向けた戦略的提携などが、企業の将来価値を決定づける鍵となる。
結論として、造船業界は今、歴史的な転換点にある。この機会を最大限に活かすためには、短期的な株価の変動に一喜二憂することなく、この構造変化の本質を深く理解し、長期的な視座に立った戦略的な投資判断を行っていくことが肝要である。今日の技術的選択が、10年後の勝者を決定づけることになるだろう。
参考文献
1 日本造船業の新造船受注残、2985万総トンに増加
https://www.kaijipress.com/news/shipbuilding/2025/06/193777
2 「日の丸造船」復活なるか? 4年連続“1100万総トン超”受注の追い風も「船台が足りない!」
https://trafficnews.jp/post/549474/2
3 我が国造船・舶用工業の現状と課題
https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001873540.pdf
4 日本造船業の手持ち工事量、3.7年分に
https://www.kaijipress.com/news/shipbuilding/2025/04/192049
5 日本造船業の新造船受注残、2985万総トンに増加
https://www.kaijipress.com/news/shipbuilding/2025/06/193777
6 「日の丸造船」復活なるか? 4年連続“1100万総トン超”受注の追い風も「船台が足りない!」
https://trafficnews.jp/post/549474/2
7 2023年の世界の新造船市場
https://www.jstra.jp/PDF/report2_2023.pdf
8 国内造船業の設備投資拡大、GX債活用で計画具体化
https://www.kaijipress.com/news/shipbuilding/2025/08/195389
9 バルチック海運指数(BDI)の長期チャート
https://chartpark.com/baltic.html
10 バルチック海運指数 – 1985-2024 データ
https://jp.tradingeconomics.com/commodity/baltic
11 我が国造船業の現状と課題
https://www.mlit.go.jp/common/001215818.pdf
12 造船業の現状と課題について
https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/uploaded/attachment/611.pdf
13 我が国海事クラスターの歴史分析
https://www.jpmac.or.jp/img/research/pdf/A201511.pdf
14 2025年度 今治造船株式会社 記者会見概要

15 海運・造船業界の動向と今後の見通し
https://www.smbc.co.jp/hojin/report/investigationlecture/resources/pdf/3_00_CRSDReport097.pdf
16 環境規制
https://www.mol.co.jp/sustainability/environment/regulation
17 環境に関わる規制
https://www.kline.co.jp/ja/sustainability/environment/regulation.html
18 EEXI/CII規制発効目前!就航船の燃費改善策の効果とは
19 国際海運からのGHG排出削減目標の強化と日本の貢献
https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001421149.pdf
20 海洋分野の動向 2021
https://www.spf.org/oceans/ocean-daily/20211223.html
21 (推論)
22 シップリサイクルとは?
https://www.mol-service.com/ja/blog/ship-recycling-1
23 欧州ガス危機とエネルギー安全保障
https://oilgas-info.jogmec.go.jp/_res/projects/default_project/page/001/009/674/230323_Research3.pdf
24 海運・造船業界の動向
https://www.hirogin-hd.co.jp/research/__icsFiles/afieldfile/2025/03/13/industry_survey_202503_1.pdf
25 貨物船市場規模、シェアおよび業界分析
https://www.fortunebusinessinsights.com/jp/%E8%B2%A8%E7%89%A9%E8%88%B9%E5%B8%82%E5%A0%B4-108601
26 2025年度 今治造船株式会社 記者会見概要

27 GX実現に向けた日本の取組
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gx_jikkou_kaigi/ikousai/dai7/siryou1.pdf
28 GX実現に向けた政府全体の予算・財政支援
https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/gx_budget.html
29 次世代船舶の開発プロジェクト
30 ゼロエミッション船等の建造促進事業、造船9社・舶用7社の計画採択
https://www.kaijipress.com/news/shipbuilding/2025/01/189771
31 株式会社ジャパンエンジンコーポレーション
32 UEエンジンとは | 株式会社ジャパンエンジンコーポレーション
https://www.j-eng.co.jp/product/ueengine.html
33 世界初、アンモニア燃料舶用エンジンの混焼運転を開始
https://www.nedo.go.jp/news/other/Z1SE_00023.html
34 次世代船舶の開発プロジェクト
35 アンモニア燃料アンモニア輸送船の建造決定
https://www.j-eng.co.jp/news/2024/l4le6t0000003113-att/J-ENG_Press_20240125_JP
36 J-ENG、アンモニアエンジン初号機10月出荷
https://www.kaijipress.com/news/shipbuilding/2025/05/192758
37 アンモニア燃料アンモニア輸送船(AFMGC)の建造を決定
https://www.nyk.com/news/2024/20240125_02.html
38 アンモニア燃料アンモニア輸送船の共同開発
https://www.classnk.or.jp/hp/ja/hp_pressrelease.aspx?id=6782&layout=1
39 China’s shipyard dominance leads to geoeconomic risks
https://www.japantimes.co.jp/commentary/2025/07/02/japan/chinas-shipyard-dominance
40 China’s shipbuilding dominance a national security risk for US: Report
41 造船業界の有名企業5選

42 三菱造船、4~12月期受注は8隻
https://www.kaijipress.com/news/shipbuilding/2025/02/190361
43 三菱造船、「海洋脱炭素グループ」を新設
https://news.kcsf.co.jp/water-mobile/20220201.html
44 三菱造船が「海洋脱炭素グループ」新設
https://merkmal-biz.jp/post/5708
45 三菱造船、「海洋脱炭素グループ」を新設
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000325.000025611.html
46 業績・業績見通し | 三菱重工業株式会社
https://www.mhi.com/jp/finance/finance/highlight
47 川重、船舶海洋とエネ・プラントを統合
https://news.kobekeizai.jp/blog-entry-7745.html
48 川崎重工が描く水素社会の未来
https://www.sustainablebrands.jp/news/1220653
49 川崎重工技報・185号
https://www.khi.co.jp/rd/magazine/pdf/185/185.pdf
50 17年ぶり造船受注2000億円超えへ川崎重工
https://www.kaijipress.com/news/shipbuilding/2025/02/190461
51 川重エネ・マリン、通期利益予想を上方修正
https://www.kaijipress.com/news/shipbuilding/2025/08/194983
52 LNG燃料大型石炭専用船「REIMEI(苓明)」
https://www.namura.co.jp/ja/product/ship/case/20231114.html
53 21万1千トン型LNG/MGO 二元燃料ばら積み運搬船「SG SUNRISE」
https://www.namura.co.jp/ja/product/ship/case/20250325.html
54 名村造船所 決算情報
https://finance.matsui.co.jp/stock/7014/settlement/index
55 名村造船所 株価
56 専業造船・舶用株が上昇
https://www.kaijipress.com/column/aotou/2025/08/195050
57 LNG燃料大型ばら積み船の建造発注を決定
https://www.nyk.com/news/2022/20220114_01.html
58 名村造船所/21.1万トン型ばら積み運搬船が竣工、日本郵船向け
https://www.lnews.jp/2025/03/r0325605.html
59 名村造船所/初のLNG・MGO二元燃料大型石炭専用船が竣工
https://www.lnews.jp/2023/11/p1114503.html
60 名村造船所 決算分析
https://note.com/ipponclub/n/n1a57c1b9b503
61 日本の造船会社と造船所の一覧
62 24年度は最高益、純利益199億円 JMU
https://www.kaijipress.com/news/shipbuilding/2025/05/192612
63 ダイハツディーゼル中日本
https://nega.or.jp/publication/press/2011/pdf/2011_09_10.pdf
64 ダイハツディーゼル、メタノールエンジン26年商用化へ
https://www.kaijipress.com/news/shipbuilding/2024/02/181582
65 舶用製品 | ダイハツインフィニアース株式会社
https://www.d-infi.com/products/marine.html
66 ダイハツインフィニアース 決算情報
https://finance.matsui.co.jp/stock/6023/settlement/index
67 ダイハツインフィニアース 株価詳細
https://finance.yahoo.co.jp/quote/6023.T
68 ダイハツインフィニアース 株価
69 世界初のアンモニア燃料タグボート「魁」が実運航を開始
https://green-innovation.nedo.go.jp/article/ammonia-fueled-tugboat
70 ジャパンエンジンコーポレーションの取組み
https://www.jpmac.or.jp/data/maritime_commission_no03/document04.pdf
71 Analysing the future cost of green hydrogen
72 Hydrogen Insights 2023 December Update
https://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2023/12/Hydrogen-Insights-Dec-2023-Update.pdf
73 国際海運の2050年CN実現に向けた 我が国の取組
https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001740220.pdf
74 2025 Midyear Economic Outlook: A Widespread Deceleration
https://www.morganstanley.com/insights/articles/economic-outlook-midyear-2025
75 Global economic outlook 2025
https://www.deloitte.com/us/en/insights/topics/economy/global-economic-outlook-2025.html
76 The Global Economy Enters a New Era
https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2025/04/22/the-global-economy-enters-a-new-era
77 世界初のアンモニア燃料船を創る海技者の視点
https://www.nyk.com/stories/04/01/20250514.html
78 The green shipping fuel everyone’s betting on, but no one can agree on
79 Unlocking markets with large-scale renewable hydrogen supply chains
80 Hydrogen Energy Supply Chain project viability remains uncertain
81 中国造船業、なぜ世界一に?
https://merkmal-biz.jp/post/100244/2
82 Geopolitical Implications of the South China Sea Disputes
https://diplomatist.com/2024/09/27/geopoliticalimplicationsofthesouthchinaseadisputes
83 The Geopolitics of Trade: Threats to Maritime Chokepoints
84 When Sea Corridors Trap the Supply Chain

85 Economic conditions outlook, June 2025